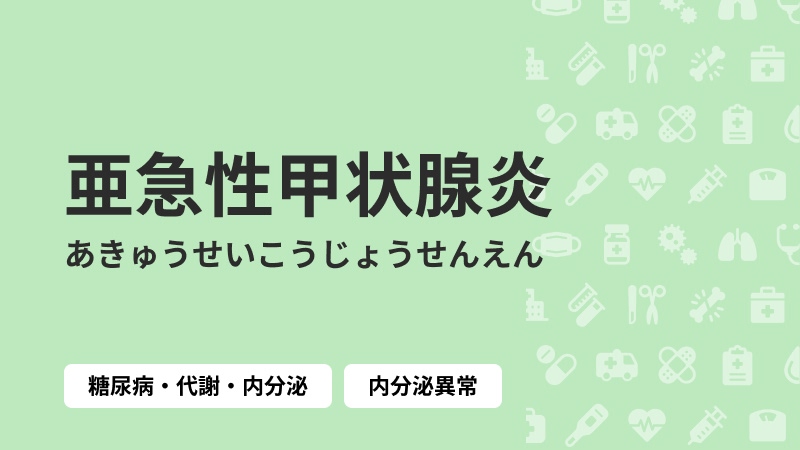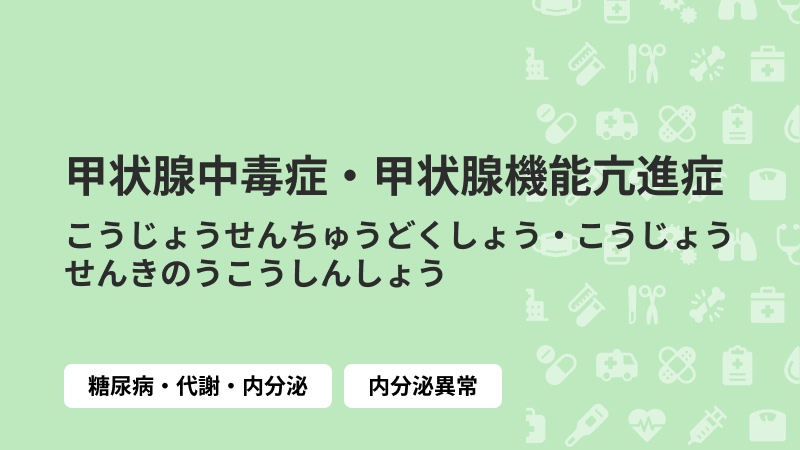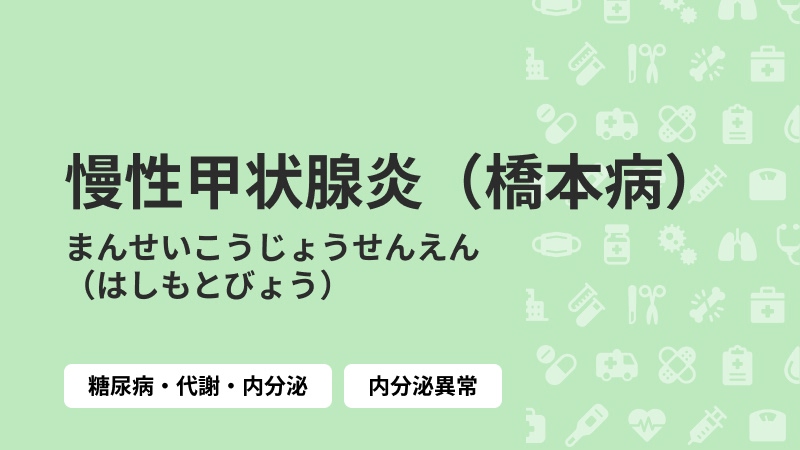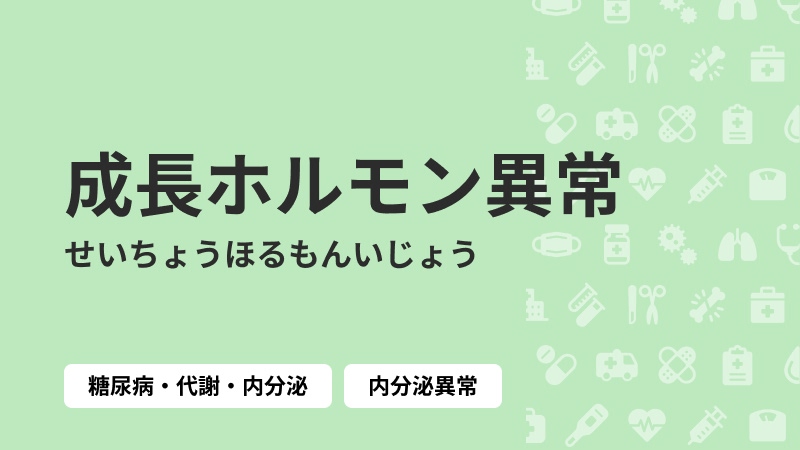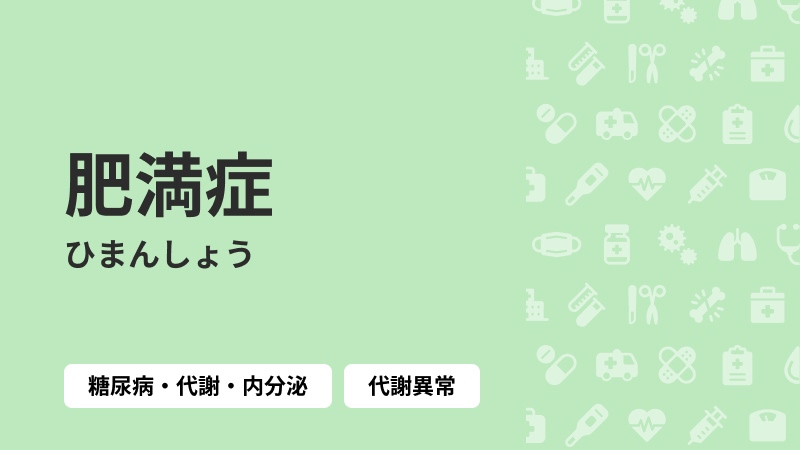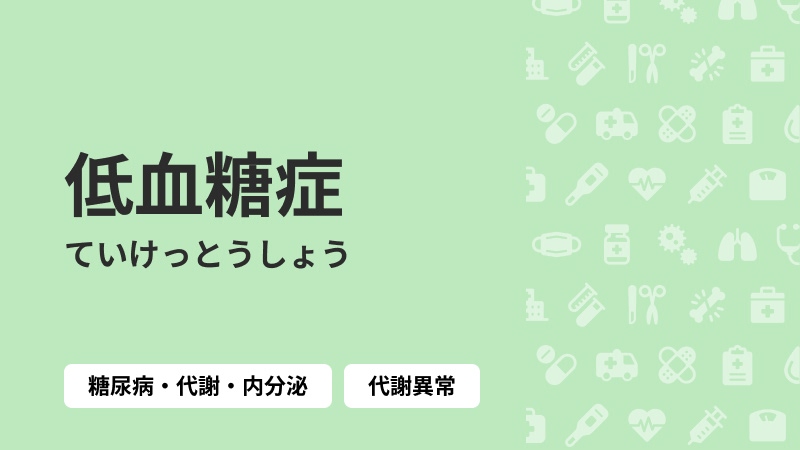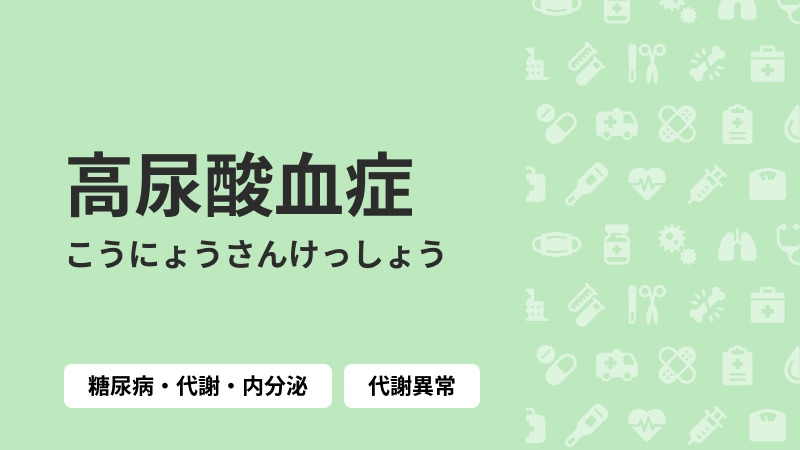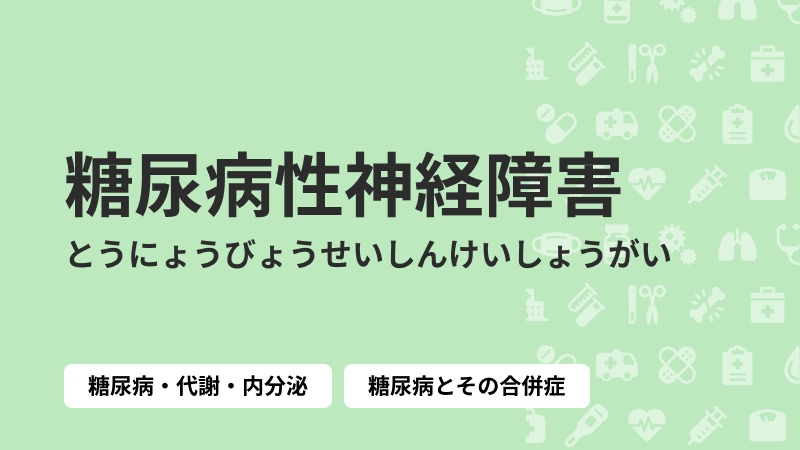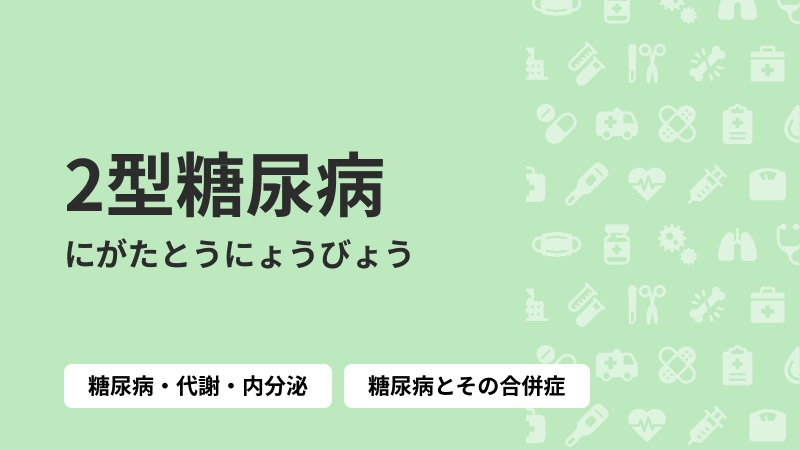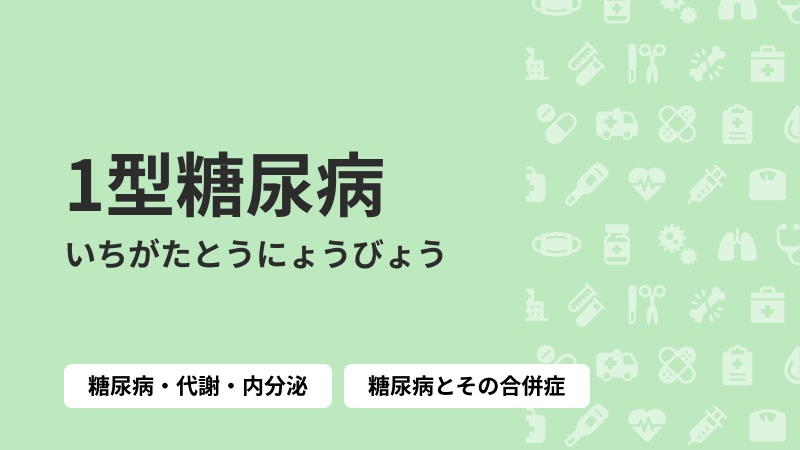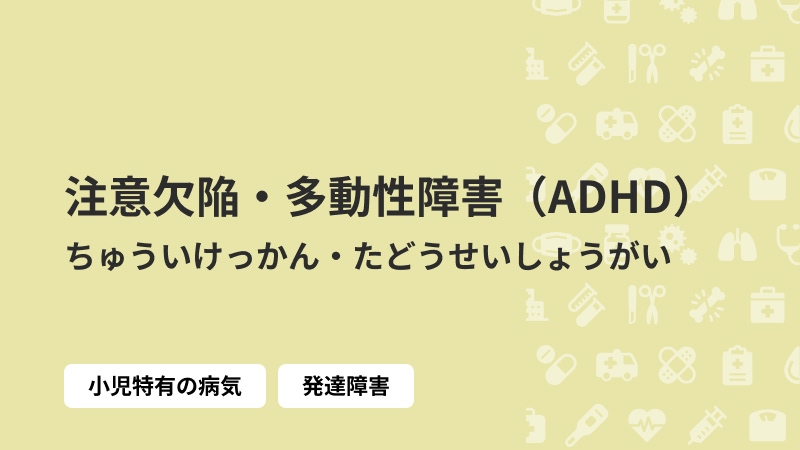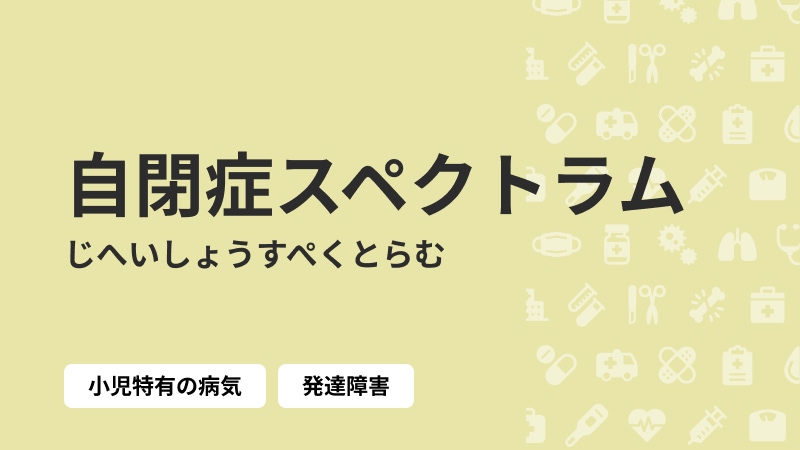病気一覧
病気症状ナビでは現役医師が監修し、病気や症状についてわかりやすく伝えています。
症状や原因、対処方法を調べることができます。
該当 189件21~40件を表示
亜急性甲状腺炎あきゅうせいこうじょうせんえん
亜急性甲状腺炎は、ウイルス感染の後などに甲状腺に炎症が生じ、一時的に甲状腺ホルモンが過剰に放出される病気です。発熱と甲状腺の痛みが特徴で、自然軽快することが多いものの、適切な対症療法が重要です。
甲状腺中毒症・甲状腺機能亢進症こうじょうせんちゅうどくしょう・こうじょうせんきのうこうしんしょう
甲状腺中毒症・甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、代謝が異常に高まる状態を指します。動悸や体重減少、発汗、精神不安などの症状が現れ、主な原因はバセドウ病です。適切な治療により多くはコントロール可能です。
慢性甲状腺炎(橋本病)まんせいこうじょうせんえん
慢性甲状腺炎(橋本病)は、自己免疫反応によって甲状腺が徐々に破壊され、甲状腺ホルモンの分泌が低下する病気です。女性に多く、倦怠感や体重増加、寒がりなどの症状が現れます。ホルモン補充治療により日常生活を支障なく送ることが可能です。
成長ホルモン異常せいちょうほるもんいじょう
成長ホルモン異常は、成長ホルモンの分泌過剰または分泌不足によって、身体の成長や代謝に異常が生じる疾患群です。小児では低身長や発育障害、成人では筋力低下や脂肪増加などを呈し、早期の診断とホルモン補充治療が重要です。
脱水症だっすいしょう
脱水症は、体内の水分と電解質のバランスが崩れた状態で、軽度から重度まで幅広く、生命に関わることもあります。特に高齢者や乳幼児では症状が出にくいため、こまめな水分補給と早期の対応が重要です。
小児肥満しょうにひまん
小児肥満は、成長期の子どもにおいて体脂肪が過剰に蓄積された状態を指します。生活習慣の影響が大きく、将来的な生活習慣病や心理的問題のリスクを高めるため、早期の介入と家庭・学校での一体的な対策が重要です。
ビタミン欠乏症びたみんけつぼうしょう
ビタミン欠乏症とは、体に必要なビタミンが不足し、さまざまな身体機能に障害が生じる状態です。ビタミンごとに特有の症状があり、食生活の乱れや吸収障害、過度なダイエットなどが主な原因です。早期の補充と原因への対処が重要です。
低血糖症ていけっとうしょう
低血糖症とは、血糖値が異常に低下することで、全身にさまざまな症状が現れる状態です。糖尿病の治療中に多く見られますが、空腹や過度の運動、アルコール摂取でも起こることがあります。早期の補食と適切な治療が重要です。
高尿酸血症こうにょうさんけっしょう
高尿酸血症は、血液中の尿酸が慢性的に高い状態を指し、放置すると痛風発作や尿路結石、腎障害などの合併症を引き起こします。生活習慣の見直しと必要に応じた薬物療法により、尿酸値の管理と発作予防が可能です。
メタボリックシンドロームめたぼりっくしんどろーむ
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積に加えて、高血圧・脂質異常・高血糖のいずれかを合併している状態を指します。動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながるリスクが高いため、早期発見と生活習慣の改善が重要です。
糖尿病性神経障害とうにょうびょうせいしんけいしょうがい
糖尿病性神経障害は、慢性的な高血糖によって末梢神経や自律神経が障害される糖尿病の三大合併症のひとつです。手足のしびれや痛みに加えて、胃腸や膀胱の機能にも影響が出ることがあります。血糖管理と適切な対症療法が重要です。
2型糖尿病にがたとうにょうびょう
2型糖尿病は、インスリンの分泌不足や効きにくさによって血糖値が慢性的に高くなる病気です。生活習慣との関連が強く、初期は無症状でも放置すると合併症を引き起こします。食事や運動などの生活習慣改善と薬物療法での血糖管理が重要です。
1型糖尿病いちがたとうにょうびょう
1型糖尿病は、自己免疫反応などによって膵臓のインスリン分泌が失われる疾患です。突然の発症が多く、血糖を下げるホルモンであるインスリンが不足するため、インスリン注射による継続的な治療が不可欠です。早期診断と血糖コントロールが合併症の予防に重要です。
注意欠陥・多動性障害(ADHD)ちゅういけっかん・たどうせいしょうがい
注意欠陥・多動性障害(ADHD)は、不注意、多動性、衝動性といった特徴が見られる発達障害のひとつです。子どもだけでなく大人にも症状が続くことがあり、日常生活や社会生活に支障をきたす場合には診断と支援が重要になります。
自閉症スペクトラムじへいしょうすぺくとらむ
自閉症スペクトラム(ASD)は、対人関係の困難や強いこだわりなどを特徴とする発達障害のひとつです。個々の特性に応じて症状の現れ方はさまざまで、早期発見と適切な支援が重要です。療育、教育、社会的サポートにより生活の質の向上が図れます。