症状から探す
息切れに関する病気一覧
息切れに関する病気をまとめています。息切れを伴うさまざまな病気の症状や原因、対処法を調べることができます。
該当 32件1~20件を表示
甲状腺中毒症・甲状腺機能亢進症こうじょうせんちゅうどくしょう・こうじょうせんきのうこうしんしょう
甲状腺中毒症・甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、代謝が異常に高まる状態を指します。動悸や体重減少、発汗、精神不安などの症状が現れ、主な原因はバセドウ病です。適切な治療により多くはコントロール可能です。
メタボリックシンドロームめたぼりっくしんどろーむ
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積に加えて、高血圧・脂質異常・高血糖のいずれかを合併している状態を指します。動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながるリスクが高いため、早期発見と生活習慣の改善が重要です。
漏斗胸(胸郭変形)ろうときょう
漏斗胸は胸骨が内側に凹む胸郭の先天性変形で、見た目だけでなく、心肺機能にも影響を及ぼすことがあります。多くは小児期に発症し、成長とともに進行するため、重症例では手術を検討します。ナス法などの矯正術が有効です。
塵肺じんぱい
塵肺は、長期にわたり粉塵を吸入することで肺に炎症と線維化を引き起こす職業性疾患です。主に鉱山や建設、鋳造業などで見られ、呼吸器症状と全身症状を呈します。早期発見と職場環境の改善が重要で、進行例では呼吸不全や合併症のリスクがあります。
嚢胞性肺疾患(肺嚢胞症)のうほうせいはいしっかん
嚢胞性肺疾患(肺嚢胞症)は、肺に空気を含む嚢胞が形成される疾患群で、自然気胸や呼吸機能障害を引き起こすことがあります。先天性や後天性を問わず原因は多岐にわたり、正確な診断と定期的なフォローが重要です。多くの場合、画像診断が決め手となります。
急性間質性肺炎きゅうせいかんしつせいはいえん
急性間質性肺炎(AIP)は、原因不明の急性発症型間質性肺炎で、重篤な呼吸不全を引き起こす稀な疾患です。症状は急速に進行し、多くは集中治療や人工呼吸管理を必要とします。ステロイド治療を含む早期の専門的対応が予後を左右します。
特発性肺線維症とくはつせいはいせんいしょう
特発性肺線維症(IPF)は、原因不明の肺線維化により肺の弾力性が低下し、進行性に呼吸機能が低下する間質性肺疾患です。労作時の息切れや乾いた咳が主症状で、治療には抗線維化薬や在宅酸素療法が用いられます。早期診断と継続的管理が必要です。
リンパ球性間質性肺炎りんぱきゅうせいかんしつせいはいえん
リンパ球性間質性肺炎(LIP)は、肺間質にリンパ球が浸潤し線維化を引き起こすまれな間質性肺疾患で、膠原病や免疫疾患と関連することが多いです。進行は緩徐で、治療にはステロイドや免疫抑制薬が用いられます。早期診断と長期的管理が重要です。
特発性器質化肺炎とくはつせいきしつかはいえん
特発性器質化肺炎(COP)は、原因不明の慢性肺炎の一種で、乾いた咳や息切れが特徴です。多くはステロイド薬に反応しますが、再発もあり、慎重な経過観察が求められます。
特発性間質性肺炎とくはつせいかんしつせいはいえん
特発性間質性肺炎は、原因不明の肺間質の慢性炎症・線維化により、進行性の呼吸機能低下を引き起こす疾患群です。労作時の息切れや乾いた咳が主症状で、治療には抗線維化薬や在宅酸素療法が用いられます。早期診断と専門的管理が重要です。
小児ぜんそくしょうにぜんそく
小児ぜんそくは、気道の慢性炎症によって繰り返す咳や喘鳴、呼吸困難を起こす病気です。アレルギーが関与することが多く、発作は夜間や早朝に起こりやすい傾向があります。吸入ステロイドなどの継続治療と生活環境の整備が予防と管理の鍵です。
肺気腫はいきしゅ
肺気腫は、肺胞が破壊されて過膨張し、ガス交換機能が低下する病気で、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の一形態です。喫煙が主な原因で、進行すると息切れや呼吸困難が悪化します。禁煙と吸入薬、リハビリが治療の中心です。
無気肺むきはい
無気肺とは、肺の一部または全部がつぶれて空気を含まなくなる状態を指し、術後や気道閉塞が原因となることが多いです。呼吸困難や低酸素血症の原因となり、早期発見と原因除去、理学療法による再膨張が治療の中心です。
気管支拡張症きかんしかくちょうしょう
気管支拡張症は、気管支が異常に拡張して元に戻らなくなり、慢性的な咳や痰、繰り返す呼吸器感染を引き起こす疾患です。原因は結核後遺症や遺伝性疾患、自己免疫など多様で、CT検査による診断と長期的な感染管理が治療の中心です。
気管支喘息きかんしぜんそく
気管支喘息は、気道の慢性的な炎症によって咳や呼吸困難を引き起こす病気です。吸入薬を中心とした治療で多くはコントロール可能で、早期の対応が重要です。

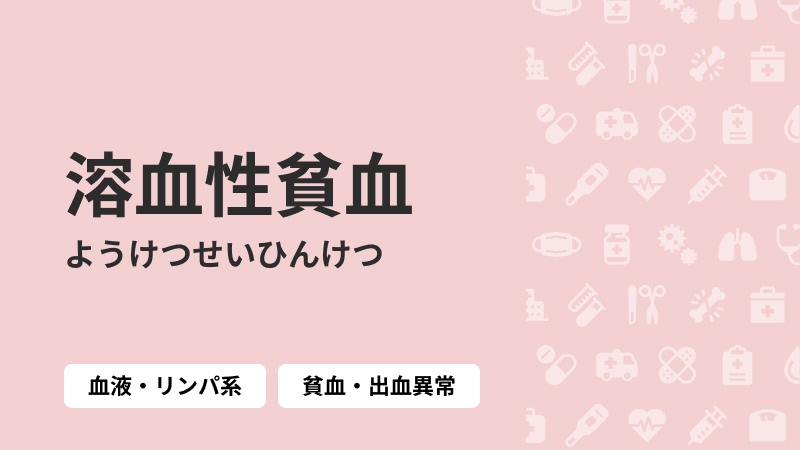
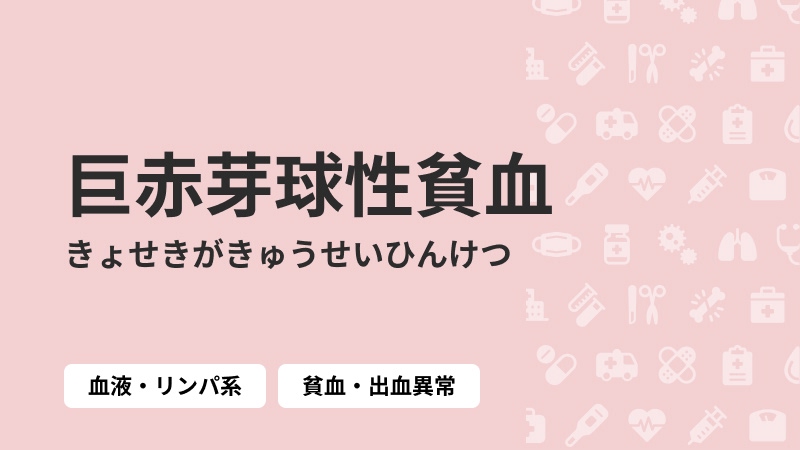
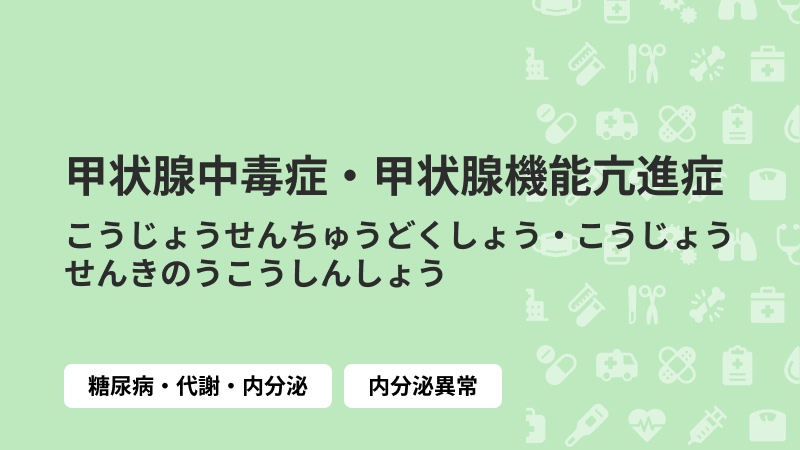

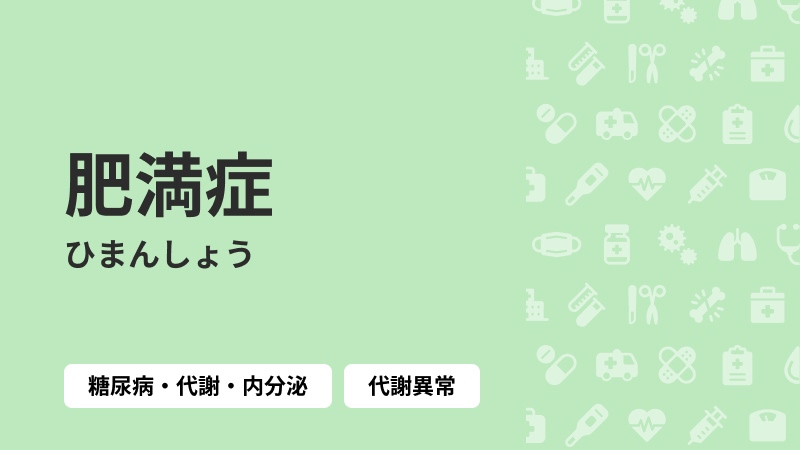


41.jpg)
38.jpg)
40.jpg)
23.jpg)
21.jpg)
22.jpg)
19.jpg)
20.jpg)
15.jpg)
16.jpg)
17.jpg)
14.jpg)
11.jpg)
