赤松 敬之医師が監修の記事一覧
赤松 敬之 医師[ 西梅田シティクリニック ]が監修した記事の一覧です。症状や原因、対処方法を調べることができます。
該当 142件41~60件を表示
ビタミン欠乏症 びたみんけつぼうしょう
ビタミン欠乏症とは、体に必要なビタミンが不足し、さまざまな身体機能に障害が生じる状態です。ビタミンごとに特有の症状があり、食生活の乱れや吸収障害、過度なダイエットなどが主な原因です。早期の補充と原因への対処が重要です。
肥満症 ひまんしょう
肥満症とは、単に体重が多いだけでなく、肥満によって健康障害や生活習慣病のリスクが高まる病態です。診断にはBMIや合併症の有無が用いられ、生活習慣の見直しと必要に応じた医療的介入が予防と治療の鍵となります。
低血糖症 ていけっとうしょう
低血糖症とは、血糖値が異常に低下することで、全身にさまざまな症状が現れる状態です。糖尿病の治療中に多く見られますが、空腹や過度の運動、アルコール摂取でも起こることがあります。早期の補食と適切な治療が重要です。
高尿酸血症 こうにょうさんけっしょう
高尿酸血症は、血液中の尿酸が慢性的に高い状態を指し、放置すると痛風発作や尿路結石、腎障害などの合併症を引き起こします。生活習慣の見直しと必要に応じた薬物療法により、尿酸値の管理と発作予防が可能です。
メタボリックシンドローム めたぼりっくしんどろーむ
メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積に加えて、高血圧・脂質異常・高血糖のいずれかを合併している状態を指します。動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの重大な病気につながるリスクが高いため、早期発見と生活習慣の改善が重要です。
糖尿病性神経障害 とうにょうびょうせいしんけいしょうがい
糖尿病性神経障害は、慢性的な高血糖によって末梢神経や自律神経が障害される糖尿病の三大合併症のひとつです。手足のしびれや痛みに加えて、胃腸や膀胱の機能にも影響が出ることがあります。血糖管理と適切な対症療法が重要です。
2型糖尿病 にがたとうにょうびょう
2型糖尿病は、インスリンの分泌不足や効きにくさによって血糖値が慢性的に高くなる病気です。生活習慣との関連が強く、初期は無症状でも放置すると合併症を引き起こします。食事や運動などの生活習慣改善と薬物療法での血糖管理が重要です。
1型糖尿病 いちがたとうにょうびょう
1型糖尿病は、自己免疫反応などによって膵臓のインスリン分泌が失われる疾患です。突然の発症が多く、血糖を下げるホルモンであるインスリンが不足するため、インスリン注射による継続的な治療が不可欠です。早期診断と血糖コントロールが合併症の予防に重要です。
脾腫 ひしゅ
脾腫とは、脾臓が異常に腫大した状態を指し、無症状で見つかることもありますが、基礎疾患として感染症、血液疾患、肝疾患などが関与している場合があります。脾腫自体の治療よりも原因疾患の診断と治療が重要となります。
良性肝腫瘍 りょうせいかんしゅよう
良性肝腫瘍とは、肝臓に発生する腫瘍のうち、がん化の可能性が低い腫瘍の総称です。多くは無症状で、健康診断や画像検査で偶然発見されます。種類によっては経過観察が中心ですが、まれに手術が必要になることもあります。
C型肝炎 しーがたかんえん
C型肝炎はC型肝炎ウイルス(HCV)によって引き起こされる感染症で、主に血液を介して感染し、慢性化しやすいのが特徴です。長期間にわたって肝機能にダメージを与え、肝硬変や肝がんに進行することがあるため、早期発見と抗ウイルス薬による治療が重要です。
B型肝炎 びーがたかんえん
B型肝炎はB型肝炎ウイルス(HBV)の感染によって引き起こされる感染症で、血液や体液を介して感染します。急性肝炎として発症する場合もあれば、慢性化して肝硬変や肝がんに進行することもあり、早期の検査と適切な治療、ワクチンによる予防が重要です。
A型肝炎 えーがたかんえん
A型肝炎はA型肝炎ウイルス(HAV)によって引き起こされる急性肝炎で、主に汚染された水や食品を介して感染します。発熱や黄疸などの症状を伴い、通常は自然に治癒しますが、高齢者では重症化することもあります。予防にはワクチン接種と衛生管理が重要です。
肝硬変 かんこうへん
肝硬変は、慢性的な肝障害が続いた結果として肝臓の組織が線維化し、機能が著しく低下する状態です。初期は無症状でも、進行すると黄疸や腹水、意識障害などの合併症が現れ、命に関わることもあります。早期の診断と原因に応じた治療が重要です。
薬物性肝障害 やくぶつせいかんしょうがい
薬物性肝障害とは、薬やサプリメントの成分によって肝臓が傷害される病気で、軽度の肝機能異常から重篤な肝炎・肝不全までさまざまな形で現れます。早期発見と原因薬剤の中止が重要であり、自己判断による薬の服用には注意が必要です。
アルコール性肝硬変 あるこーるせいかんこうへん
アルコール性肝硬変とは、長期間の多量飲酒によって肝臓に線維化が進行し、肝機能が著しく低下した状態です。自覚症状が少ない初期を経て、黄疸や腹水、肝性脳症などの重篤な合併症が現れます。禁酒と適切な治療によって進行を抑えることが可能です。
アルコール性肝障害 あるこーるせいかんしょうがい
アルコール性肝障害とは、長期にわたる過剰な飲酒によって肝臓が慢性的に障害される状態で、脂肪肝から肝炎、肝線維症、肝硬変、肝がんへと進行します。早期には無症状のことが多く、禁酒と生活改善による早期対応が肝機能の回復と進行防止の鍵となります。
アルコール性肝線維症 あるこーるせいかんせんいしょう
アルコール性肝線維症とは、長期にわたる過剰な飲酒によって肝臓の組織が硬くなり、正常な肝機能が損なわれていく状態です。自覚症状が乏しいまま進行し、最終的には肝硬変に至る危険性があります。完全禁酒と生活習慣の改善が進行を防ぐ鍵です。




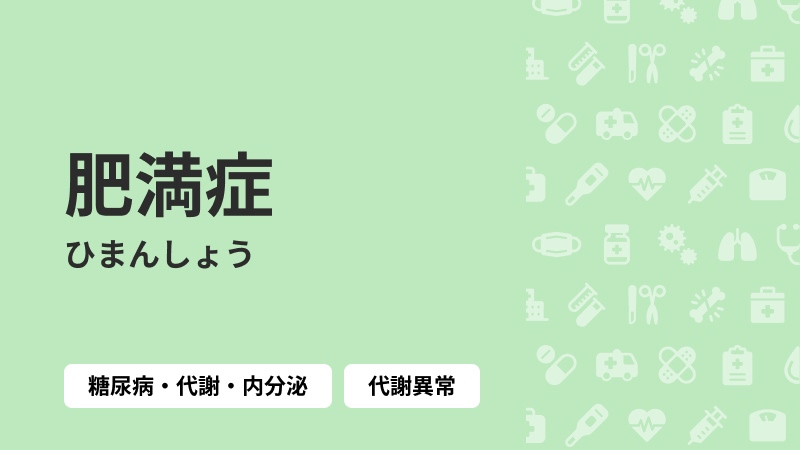
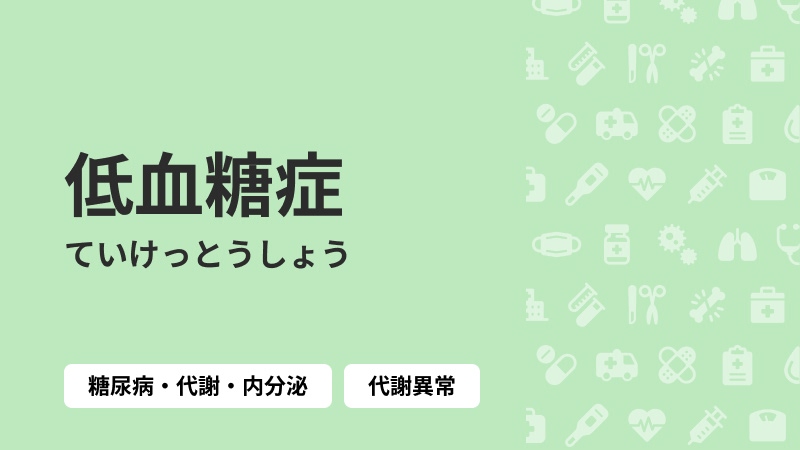
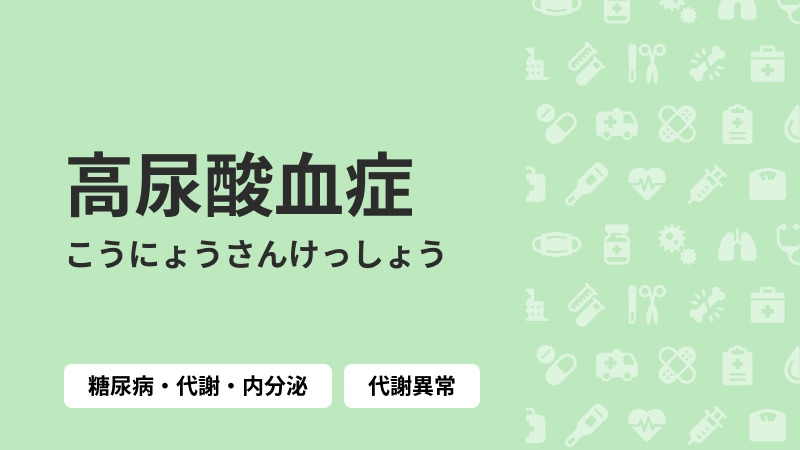

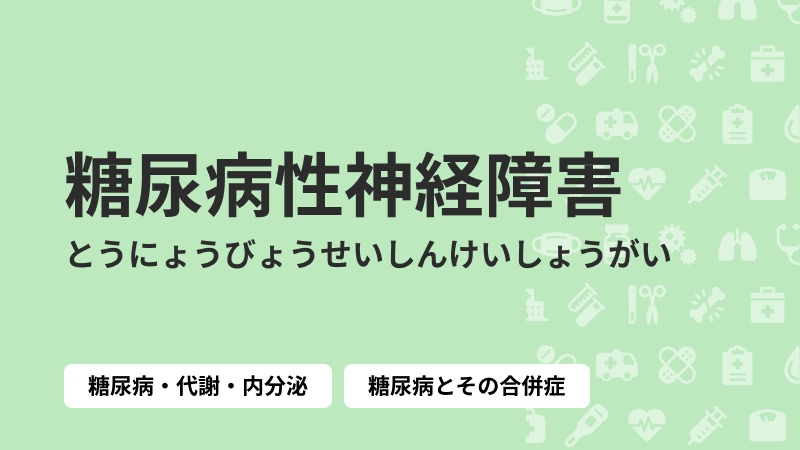
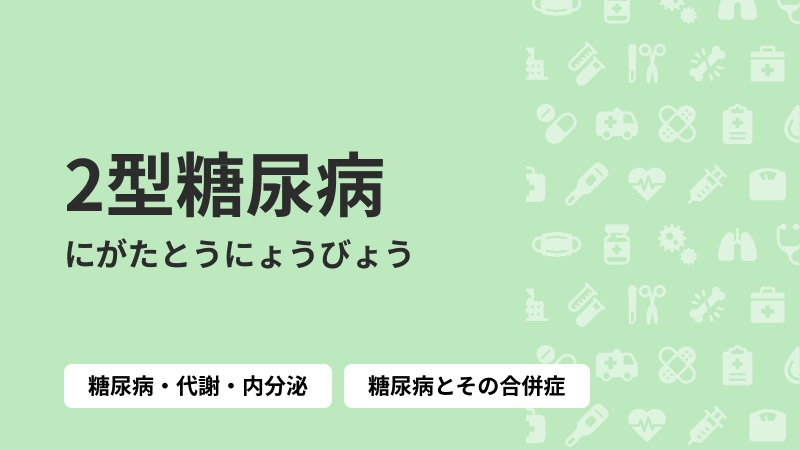
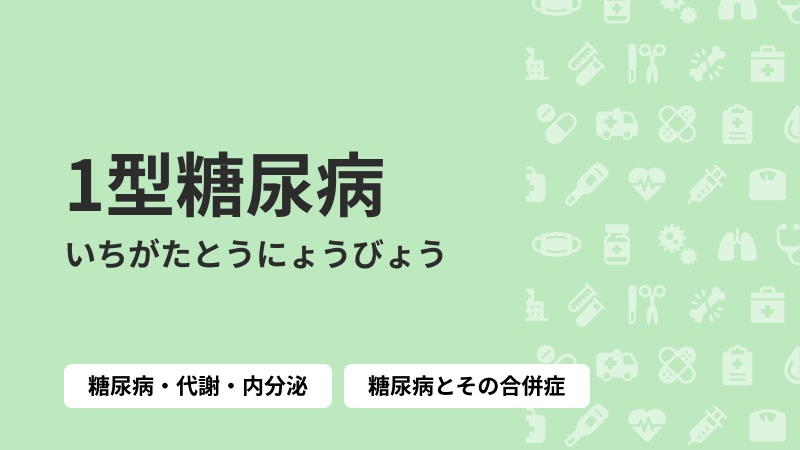
86.jpg)
85.jpg)
84.jpg)
83.jpg)
82.jpg)
81.jpg)
80.jpg)
79.jpg)
78-1.jpg)
77.jpg)
