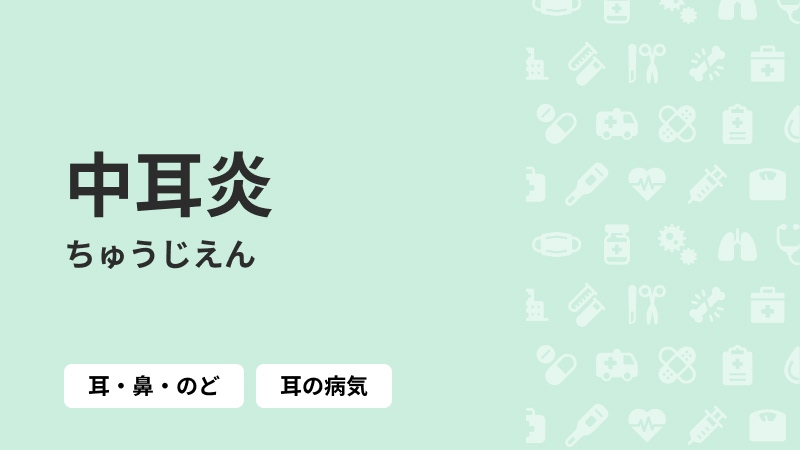症状から探す
気分や心の反応に関する病気一覧
該当 46件21~40件を表示
胃・十二指腸潰瘍穿孔い・じゅうにしちょうかいようせんこう
胃・十二指腸潰瘍穿孔は、消化性潰瘍が深く進行し、胃や十二指腸の壁に穴が開く緊急性の高い病態です。突然の激しい腹痛で発症し、腹膜炎やショックを伴うこともあります。治療は原則として緊急手術が必要で、迅速な診断と処置が生死を分けることがあります。ピロリ菌やNSAIDsなど原因への対応と、早期受診が命を守る鍵となります。
漏斗胸(胸郭変形)ろうときょう
漏斗胸は胸骨が内側に凹む胸郭の先天性変形で、見た目だけでなく、心肺機能にも影響を及ぼすことがあります。多くは小児期に発症し、成長とともに進行するため、重症例では手術を検討します。ナス法などの矯正術が有効です。
アナフィラキシーショックあなふぃらきしーしょっく
アナフィラキシーショックは、アレルギー反応の中でも最も重篤な症状で、血圧低下や意識障害、呼吸困難を急速に引き起こします。食物や薬物、昆虫毒が主な原因で、迅速なアドレナリン投与と救急対応が命を守る鍵となります。
睡眠時無呼吸症候群すいみんじむこきゅうしょうこうぐん
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に繰り返し呼吸が止まる疾患で、強いいびきや日中の強い眠気が特徴です。生活習慣病や事故のリスクも高まるため、早期診断と治療が重要です。CPAP療法などの治療により症状の改善が期待されます。
緊張性気胸きんちょうせいききょう
緊張性気胸は、肺に穴が開くことで空気が胸腔に溜まり続け、肺や心臓を圧迫して重篤な呼吸・循環障害を引き起こす緊急疾患です。早期の診断と針脱気、胸腔ドレナージによる減圧処置が生死を分けます。迅速な対応が不可欠です。
過敏性腸症候群かびんせいちょうしょうこうぐん
過敏性腸症候群(IBS)は、明らかな器質的異常がないにもかかわらず、慢性的に腹痛や便通異常(下痢や便秘、あるいはその両方)を繰り返す疾患です。ストレスや自律神経の乱れが関与しており、生活の質(QOL)を著しく低下させることがあります。治療には薬物療法、生活指導、心理的アプローチが重要です。
腸閉塞ちょうへいそく
腸閉塞は、腸の内容物が通過できなくなることで、腹痛、嘔吐、排便停止などを引き起こす疾患です。癒着、腫瘍、炎症、ヘルニアなどの物理的閉塞や、腸管の運動障害が原因となります。放置すると腸管壊死や穿孔に至ることもあり、迅速な診断と適切な治療が不可欠です。
ダンピング症候群だんぴんぐしょうこうぐん
ダンピング症候群は、胃の手術後に食後の急激な血流変化や低血糖により動悸やめまい、下痢などが起こる状態です。発症時期により「早期型」と「後期型」に分類され、いずれも日常生活に影響を与えることがあります。治療は主に食事療法と生活習慣の調整で、重症例では薬物治療が検討されます。
胃神経症いしんけいしょう
胃神経症は、胃カメラなどの検査で異常が見つからないにもかかわらず、胃もたれやみぞおちの痛み、食欲不振などの症状が続く状態を指します。ストレスや自律神経の乱れが深く関係しており、機能性ディスペプシアの一種とされています。治療には薬物療法に加えて、生活習慣や心理的な側面への対応も重要です。
胃下垂いかすい
胃下垂は、胃の位置が通常よりも下がっている状態で、必ずしも病気ではありませんが、胃もたれや消化不良、便秘などの不快な症状を伴うことがあります。体質や姿勢の影響が大きく、治療は生活習慣の改善や運動療法が中心です。重症の場合は消化器内科での評価が必要です。
胃けいれんいけいれん
胃けいれんとは、胃の筋肉が一時的に強く収縮することで起こる痛みや不快感のことを指します。明確な病変がないにもかかわらず、ストレスや生活習慣、冷えなどが原因で症状が現れることが多く、胃の機能的な障害とされています。治療は薬物療法とともに、ストレス管理や生活習慣の見直しが重要です。
空気嚥下症(呑気症)くうきえんげしょう
空気嚥下症(呑気症)は、無意識に多くの空気を飲み込んでしまうことで、げっぷや腹部膨満感、胃の不快感などを引き起こす病気です。ストレスや生活習慣が原因となることが多く、治療には行動療法や生活習慣の見直し、薬物療法が用いられます。命に関わる病気ではありませんが、慢性的な不快症状が生活の質を低下させるため、適切な対応が必要です。
乳幼児突然死症候群(SIDS)にゅうようじとつぜんししょうこうぐん
乳幼児突然死症候群(SIDS)は、健康に見えた乳児が予兆なく睡眠中に突然死亡する原因不明の疾患です。生後2〜6か月に多く、うつぶせ寝や受動喫煙などがリスク要因とされています。予防には睡眠環境の整備が重要です。
肺水腫はいすいしゅ
肺水腫は、肺に液体が異常に貯留することで呼吸困難を引き起こす疾患です。多くは左心不全による心原性が原因ですが、感染や外傷などによる非心原性もあります。迅速な診断と呼吸・循環管理が生命予後に直結します。
食道・胃静脈瘤しょくどう・いじょうみゃくりゅう
食道・胃静脈瘤は、肝硬変などによって門脈の圧力が高まり、食道や胃の静脈が拡張・蛇行してできる病変です。初期は無症状ですが、破裂すると大量の吐血やショックを引き起こし、命に関わることもあります。内視鏡検査による定期的な観察と、必要に応じた治療・予防処置が不可欠です。肝疾患と密接に関連するため、全身的な管理も重要です。

24.jpg)


41.jpg)
39.jpg)
-10.jpg)
-9.jpg)
45.jpg)
56.jpg)
55.jpg)
38.jpg)
36.jpg)
34.jpg)
35.jpg)
33.jpg)
12.jpg)
52.jpg)
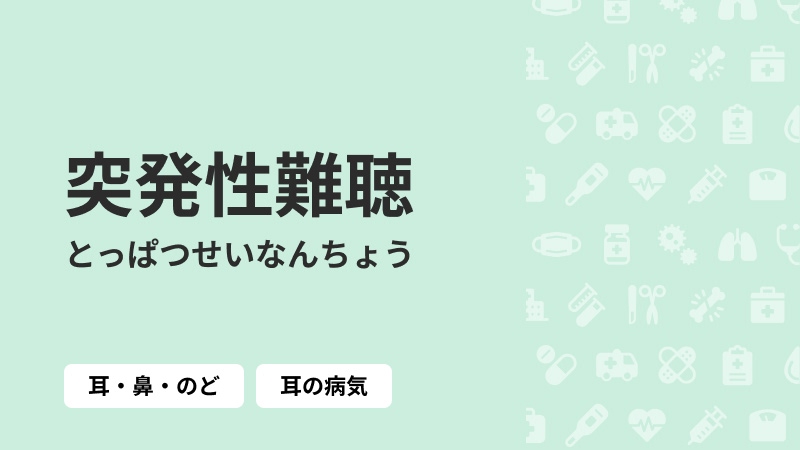
13.jpg)