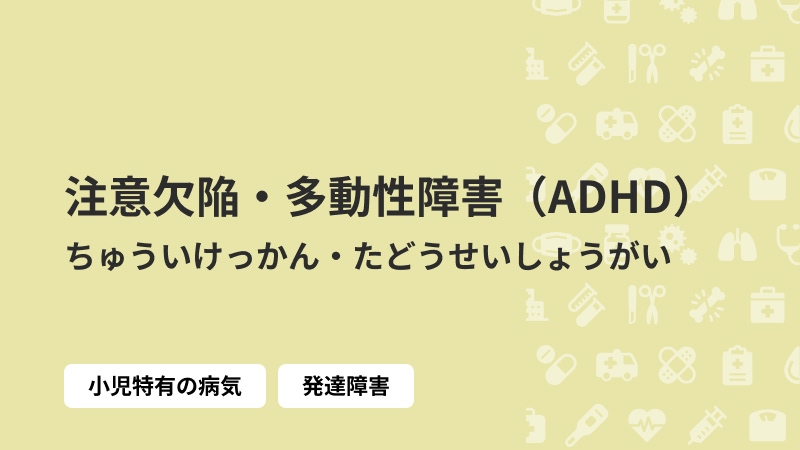自閉症スペクトラムじへいしょうすぺくとらむ
自閉症スペクトラム(ASD)は、対人関係の困難や強いこだわりなどを特徴とする発達障害のひとつです。個々の特性に応じて症状の現れ方はさまざまで、早期発見と適切な支援が重要です。療育、教育、社会的サポートにより生活の質の向上が図れます。
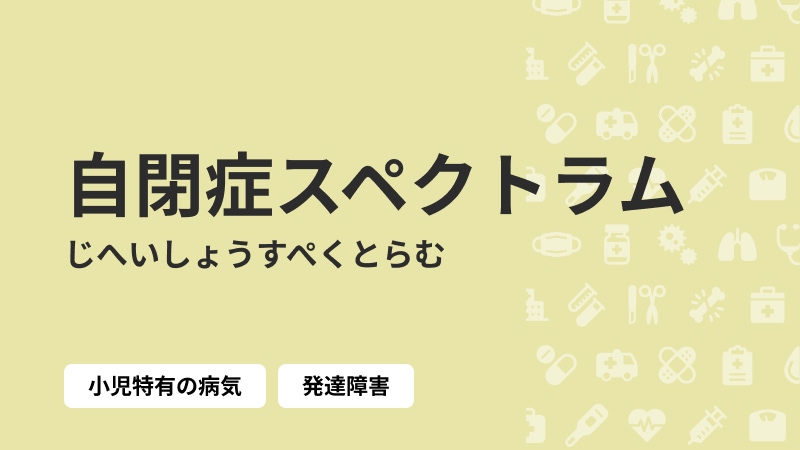
自閉症スペクトラムとは?
自閉症スペクトラム(Autism Spectrum Disorder:ASD)とは、対人関係やコミュニケーションの困難、興味や行動の偏り・こだわりなどを特徴とする発達障害の一つです。従来は「自閉症」「アスペルガー症候群」などに分類されていましたが、現在はそれらを含めた広い概念として「自閉症スペクトラム障害」と表現されます。
「スペクトラム」という言葉は、症状やその程度が人によって非常に幅広く、連続体のように多様であることを意味しています。知的障害を伴う場合もあれば、知能は平均以上でも対人関係に著しい困難がある場合もあります。
ASDは先天的な特性に起因すると考えられており、親の育て方や家庭環境が原因ではありません。生まれつきの脳の発達の違いにより、情報処理や社会的理解に偏りが生じることで、周囲と齟齬が生じやすくなります。
乳幼児期から症状が現れますが、軽度の場合は学齢期や成人になってから初めて気づかれることもあります。適切な理解と支援により、本人の力を伸ばし、よりよい社会参加が可能になります。
原因
自閉症スペクトラムの原因は、完全には解明されていませんが、主に生物学的・遺伝的な要因が関与していると考えられています。育児環境や親の愛情の有無が直接的な原因になることはありません。
主な要因
- 脳の構造と機能の違い:MRIなどの画像検査で、脳の一部(大脳皮質、小脳、辺縁系など)の発達や活動に偏りがあることが示されています。
- 神経伝達物質の異常:セロトニン、ドーパミンなど、神経間の情報伝達に関与する物質のバランスに違いがある可能性が指摘されています。
- 遺伝的要因:一卵性双生児での一致率が高いことや、家族にASDの特性を持つ人がいる確率が高いことなどから、多因子遺伝の関与が考えられています。
- 環境因子(可能性):妊娠中のウイルス感染や薬剤曝露、出産時の異常などが一部で報告されていますが、決定的な因果関係は不明です。
ASDは発症メカニズムが非常に複雑で、複数の要素が組み合わさって症状が現れると考えられています。近年の研究では遺伝子解析や脳機能の詳細な分析が進んでいますが、まだ治療法に直結する段階ではありません。
重要なのは、「生まれつきの特性」として正しく理解し、本人の困りごとに応じた支援を行うことです。
症状
自閉症スペクトラムの症状は、主に以下の2つの領域に分けられます。症状の程度や現れ方には個人差があり、年齢や発達段階によって変化することもあります。
- 社会的コミュニケーションと対人関係の困難
・視線が合いにくい
・人との距離感が不自然(近づきすぎる/避けすぎる)
・会話のやり取りがかみ合わない(話しすぎる/返答が遅れる)
・冗談や比喩、空気を読むことが苦手
・感情の表現や理解が難しい(相手の気持ちを想像しにくい)
・友だちを作るのが苦手/集団行動が苦手 - 興味や行動の偏り、こだわり
・特定のものに強い興味を示す(電車、地図、数字など)
・同じ遊びを繰り返す/同じ話題を繰り返す
・日課や手順の変化に強く抵抗する(予測できない出来事に混乱)
・特定の道順や座席などに固執
・感覚過敏(音、におい、光、肌ざわりなどに強く反応)
・逆に感覚鈍麻(痛みに鈍い、熱さに気づかない) - その他の特徴
・言葉の遅れ、または非常に語彙が豊富で一方的な話し方をする
・身体の不器用さ(運動協調性の困難)
・睡眠リズムの乱れ、偏食なども伴いやすい - 年齢による違い
・乳児期:あやしても笑わない、人見知りがない、指さしをしない
・幼児期:ごっこ遊びが苦手、集団行動になじめない
・学童期:対人関係のトラブル、パニックや癇癪が目立つ
・成人期:就労や人間関係の継続が困難になりやすい
本人は「困っていないように見える」こともありますが、周囲との違いに気づき、自信を失ってしまうケースも多くあります。
診断方法と治療方法
診断
自閉症スペクトラムの診断は、専門の医師(小児科、児童精神科、精神科など)による総合的な評価によって行われます。以下の要素をもとに診断されます。
- 問診と行動観察
・本人および保護者への詳細な聞き取り(乳幼児期からの行動、発達状況、対人関係など)
・診察時の視線、表情、反応の観察 - 発達検査・心理検査
・新版K式発達検査、田中ビネー知能検査、WISC(児童)、WAIS(成人)などを用いて知的機能や認知特性を評価 - ASDに特化した評価スケール
・ADOS-2(自閉症診断観察スケジュール)
・ADI-R(自閉症診断面接)
・CARS、M-CHAT(幼児向けスクリーニング)など - 他の発達障害・精神疾患との鑑別
・ADHD、知的障害、社交不安障害、うつ病などと区別して診断されます
治療
ASDに根本的な治療薬はありませんが、症状に応じた療育・支援によって生活の質を大きく改善することが可能です。
- 療育・教育的支援
・TEACCH(構造化教育):視覚的支援で予測性を高める
・ソーシャルスキルトレーニング(SST):対人関係の練習
・応用行動分析(ABA):望ましい行動を強化し、問題行動を減らす
・特別支援教育や通級指導、特別支援学校の利用 - 薬物療法(補助的)
・過度の不安、睡眠障害、癇癪、注意散漫などに対して抗不安薬、抗精神病薬、メラトニン製剤などが用いられることも - 家族支援・環境調整
・保護者へのペアレントトレーニング
・学校・職場との連携、理解促進
・障害福祉サービス(放課後等デイサービス、就労支援など)の活用
個々の特性を尊重し、得意・不得意を把握したうえで最適な環境を整えることが、本人の自立と社会参加への第一歩となります。
予後
自閉症スペクトラムの予後は個人差が大きく、知的水準や言語能力、支援の有無などが大きく影響します。早期に適切な支援を受けた場合、社会的な自立が可能なケースも多くあります。
良好な予後が期待される要因
- 3歳までに言葉の理解や使用が可能
- IQが中等度以上
- 行動問題が少なく、社会的興味がある
- 保護者や周囲の支援体制が整っている
課題の残る場合
- 知的障害を伴うASDでは支援の継続が必要な場合が多い
- 思春期以降に二次障害(うつ、不安、引きこもり)を合併することも
成人期には、就労・結婚・独立などの社会的課題に直面しやすく、本人の特性に合わせた職場環境や支援体制が必要です。
予後を良好に保つためには、早期診断・早期支援、継続的な見守りと柔軟な対応が欠かせません。
予防
自閉症スペクトラムは「先天的な発達特性」であるため、現時点で確立された予防法は存在しません。しかし、早期に気づき、適切な支援を受けることで、本人の発達と生活の質を大きく向上させることが可能です。
早期発見の重要性
- 乳幼児健診での気づきがカギとなる
- 「指さしをしない」「視線が合わない」「言葉が遅い」などの特徴に注目
- 心配があれば早めに自治体の発達相談窓口や小児科、発達専門医に相談する
環境整備
- 家庭や保育・教育現場で、わかりやすく予測可能な環境を整える
- 感覚過敏への配慮(音、光、素材など)
- 無理に「普通」に合わせるのではなく、特性に合った支援を意識
「予防」ではなく、「理解と適応」がASD支援の本質です。社会全体の理解が広がることで、ASDのある人の生きづらさは大きく軽減されます。
関連する病気や合併症
自閉症スペクトラムは、以下のような発達障害や精神・身体疾患と合併しやすいとされています。
発達障害との合併
- ADHD(注意欠如・多動症):集中困難、衝動性、不注意が目立つ
- 学習障害(LD):読み書き計算など特定の学習能力に困難
- 発達性協調運動障害:不器用さ、運動のぎこちなさ
精神障害との合併
- 不安障害(社交不安、強迫性障害など)
- うつ病、気分変調症(思春期以降に増加)
- 適応障害、引きこもり
神経・身体疾患
- てんかん(ASD児の約20〜30%にみられる)
- 睡眠障害
- 胃腸症状(便秘、過敏性腸症候群など)
合併症がある場合、支援や治療の優先順位を明確にし、多職種連携(医師、心理士、作業療法士、教師など)による包括的支援が重要です。ASD単独の支援では不十分なこともあるため、個々の症状に応じた対応が必要です。
症状が気になる場合や、体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。

クラウドドクターの
オンライン診療
クラウドドクターのオンライン診療
クラウドドクターでは、問診内容を元に全国から適したドクターがマッチングされ、あなたの診療を行います。診療からお薬の処方までビデオ通話で受けられるため、お忙しい方にもおすすめです。
-
24時間365日
いつでも診療OK -
保険診療が
ご利用可能 -
お近くの薬局やご自宅で
お薬の受取り可能
■ 参考・出典
日本自閉症協会「自閉症スペクトラムの理解と支援」
(https://www.autism.or.jp/)
MSDマニュアル プロフェッショナル版「自閉症スペクトラム障害」
(https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional)
厚生労働省 e-ヘルスネット「発達障害」(https://kennet.mhlw.go.jp/home)
■ この記事を監修した医師

鄭 賢樹医師 てい小児科クリニック
近畿大学 医学部 卒
守口敬仁会病院で消化器外科医として研鑽を積んだのち、りんくう総合医療センター救命診療科で外傷・集中治療に従事。在宅医療専門クリニック「グリーングラス」では訪問診療に携わり、大手美容皮膚科・医療痩身クリニックでは美容医療の経験も重ねてきた。急性期医療から慢性疾患管理、美容領域、さらには在宅医療に至るまで、幅広い分野を経験。
2024年より「てい小児科クリニック」に赴任。小児科を長年支えてきた父の志を受け継ぎながら、内科、美容皮膚科、医療痩身、訪問診療を新たに導入し、地域に寄り添う“人生まるごと”の医療を提供することを目指している。
モットーは「医療を介して地域と絆でつながる」こと。
そして、「患者さま以上に、患者さまの健康を想う」こと。
日々の診療の中で、「今日も、あなたの“これから”を支えたい」という想いを胸に、子どもから高齢者まで、すべての世代の健康を全力で支える医療に取り組んでいる。
- 公開日:2025/09/19
- 更新日:2025/09/19
クラウドドクターは24時間365日対応
現在の待ち時間
約3分