直腸脱ちょくちょうだつ
直腸脱は、直腸が肛門の外へ突出する状態で、高齢者や出産歴のある女性に多く見られます。排便障害や便失禁を引き起こし、生活の質を低下させます。重症例では手術が必要であり、早期診断と骨盤底筋のケアが重要です。
64.jpg)
直腸脱とは?
直腸脱とは、直腸が肛門を通じて体外に突出する状態を指します。腸管の内側から外へと反転するように押し出されるこの病態は、排便時や腹圧がかかった際に起こりやすく、進行すると常時脱出したままになることもあります。
直腸の粘膜のみが脱出する「粘膜脱」と、直腸全層が脱出する「全層直腸脱」があり、前者は軽度であり、後者は進行した状態です。さらに、軽度の段階では排便時のみの一時的な脱出で自然に戻りますが、重度になると手で押し戻さなければ戻らなくなり、最終的には常時脱出する「非還納性直腸脱」へと進行します。
この疾患は女性に多く、特に高齢者や出産歴のある女性、慢性の便秘や下痢がある人に発症しやすい傾向があります。骨盤底筋の弛緩や支持組織の脆弱化が背景にあるとされており、生活の質(QOL)に大きな影響を与える疾患です。
原因
直腸脱の主な原因は、骨盤底の支持組織の緩みや筋力の低下です。加齢に伴い、骨盤底筋群の筋力が低下し、直腸や肛門周囲の支持構造が弱くなると、腸が肛門側に滑り込みやすくなります。特に女性では、妊娠・出産に伴う骨盤底への負担がその後のリスク因子となります。
また、慢性の便秘や排便時の強いいきみ、下痢などによる長年の腹圧負荷も原因となります。過度の排便習慣は肛門括約筋や直腸の支持組織を損傷し、徐々に直腸脱の進行を助長します。
神経障害も関与していると考えられており、脊髄損傷や糖尿病、パーキンソン病などの患者では、排便機能の異常が骨盤底の緩みに拍車をかけることがあります。また、先天的な解剖学的異常(直腸の長さや角度)や遺伝的素因も一部関与が示唆されています。
いずれの原因も複合的に作用することが多く、年齢、性別、体格、既往歴、生活習慣などを総合的に評価する必要があります。
症状
直腸脱の症状は、軽度では排便時に肛門から赤く湿った組織(直腸粘膜や直腸壁)が一時的に突出するだけですが、進行すると手で戻さないと元に戻らない、または常時脱出したままになることがあります。
もっとも特徴的な症状は、肛門からの腸の脱出です。初期には排便時や強くいきんだときにのみ認められますが、次第に歩行や立ち上がりといった日常動作でも起こるようになります。
その他の症状としては、肛門周囲の不快感、湿潤感、出血、排便時のしぶり感、残便感などがあり、慢性的な便通異常(便秘と下痢の反復)を伴うこともあります。
重度の直腸脱では、括約筋が引き伸ばされることで便失禁(ガスや液体便の漏れ)を起こすことがあり、日常生活に大きな支障をきたします。また、脱出した直腸がうっ血し、腫れて戻らなくなる「嵌頓(かんとん)」を起こすと、激しい痛みや出血、さらには壊死のリスクも生じます。
皮膚炎や潰瘍、感染などを伴うこともあり、局所の皮膚状態が悪化し、衛生面・精神面の負担が大きくなります。
こうした症状はゆっくり進行することが多く、恥ずかしさから受診をためらう患者も多いため、早期発見・早期治療のためには医療者の積極的な関与と患者への理解が重要です。
診断方法と治療方法
診断
診断は、問診と視診・触診が中心です。問診では、症状の出現時期、排便習慣、便失禁の有無、出産歴や手術歴、既往症などを詳しく確認します。視診では、排便姿勢を再現した状態で肛門からの突出の有無や状態を確認します。
軽度の直腸脱では排便時のみの脱出であるため、診察時に脱出が見られないこともあります。その場合、排便造影検査(defecography)や超音波、MRIなどを用いて、肛門周囲の動態や直腸の下垂を評価します。
直腸機能や肛門括約筋の圧力を測定する「肛門内圧検査」や「筋電図」なども、手術適応の判断材料として行われます。また、便失禁の合併がある場合には、その評価と対策が同時に必要です。
治療
治療は症状の程度と患者の希望に応じて段階的に行われます。
保存的治療
軽度であれば、骨盤底筋体操(Kegel体操)や排便習慣の改善、便秘の解消などで症状の進行を防ぐことが可能です。排便補助器具の使用や便軟化剤の投与も行われます。
手術療法
中等度以上、または日常生活に支障をきたす場合には手術が選択されます。手術方法は多岐にわたり、大きく「腹式手術(直腸固定術)」と「会陰式手術(直腸切除・縫縮術など)」に分けられます。
腹式は再発が少ない一方で体への負担が大きく、若年者や再発例に適しています。会陰式は高齢者や合併症のある患者にも対応しやすい手技であり、負担の少ない選択肢としてよく用いられます。
予後
直腸脱の予後は、早期に適切な治療が行われれば良好です。特に手術療法を受けた患者では、多くの場合で症状が改善し、日常生活の質が向上します。再発率は手術法により異なりますが、腹式直腸固定術では5〜10%、会陰式手術では20〜30%程度とされています。
術後の注意点としては、便秘や強いいきみを避けることが挙げられます。再発予防のためには、排便習慣の見直しと骨盤底筋のトレーニングが重要です。特に高齢者では筋力の回復が遅れることもあり、継続的なリハビリが勧められます。
また、便失禁が合併していた場合には、手術後にその改善が期待されますが、完全に治るとは限らず、残存するケースもあります。定期的なフォローアップと、必要に応じた生活指導やリハビリテーションの継続が求められます。
高齢者や基礎疾患のある患者では、再発や合併症のリスクも考慮しつつ、QOLを重視した個別対応が必要です。
予防
直腸脱の予防には、骨盤底の筋力維持と、排便習慣の改善が重要です。特に、慢性便秘のある人は、排便時の過度ないきみが直腸脱のリスクを高めるため、適切な排便指導と便通管理が不可欠です。
日常生活では、以下のような対策が予防に有効です。
- バランスの取れた食事で食物繊維をしっかり摂取する
- 水分を十分に摂る
- 毎日適度な運動(ウォーキングやスクワットなど)を行う
- トイレで長時間座らない
- 排便を我慢しない
骨盤底筋体操(Kegel体操)は、排便コントロールの改善だけでなく、再発予防にも有効です。出産後の女性や高齢者では、日常的なトレーニングとして取り入れることが推奨されます。
また、早期の症状(肛門周囲の違和感、脱出感)があれば、恥ずかしがらずに早期に医療機関を受診することが、進行の抑制につながります。
関連する病気や合併症
直腸脱は、単独で発症することもありますが、しばしば他の骨盤底障害や消化器疾患と合併することがあります。とくに「直腸瘤」や「膀胱瘤」、「子宮脱」などの骨盤臓器脱と同時に起こるケースが多く、これらは骨盤底全体の支持構造が弱くなっていることを示しています。
また、慢性便秘や排便障害との関連も強く、排便時の長時間のいきみによって、脱出が助長されることがあります。逆に、直腸脱が原因で排便しづらくなり、便秘が悪化するという悪循環に陥ることもあります。
直腸脱による便失禁は、社会的な活動制限を招くだけでなく、心理的負担やうつ症状の原因にもなります。皮膚の炎症、潰瘍、感染といった局所的な合併症にも注意が必要です。
診断時には、他の肛門疾患(痔核、痔瘻、直腸癌など)との鑑別も重要です。多くの患者では複数の問題が同時に存在するため、包括的な評価と治療方針の検討が求められます。
症状が気になる場合や、体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。

クラウドドクターの
オンライン診療
クラウドドクターのオンライン診療
クラウドドクターでは、問診内容を元に全国から適したドクターがマッチングされ、あなたの診療を行います。診療からお薬の処方までビデオ通話で受けられるため、お忙しい方にもおすすめです。
-
24時間365日
いつでも診療OK -
保険診療が
ご利用可能 -
お近くの薬局やご自宅で
お薬の受取り可能
■ 参考・出典
日本大腸肛門病学会「直腸脱の診断と治療」
(https://www.coloproctology.gr.jp/)
MSDマニュアル プロフェッショナル版「直腸脱」
(https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional)
日本外科学会「肛門疾患とその管理」
(https://www.jssoc.or.jp/)
■ この記事を監修した医師

赤松 敬之医師 西梅田シティクリニック
近畿大学 医学部 卒
近畿大学医学部卒業。
済生会茨木病院にて内科・外科全般を担当。
その後、三木山陽病院にて消化器内科・糖尿病内科を中心に、内視鏡を含む内科全般にわたり研鑽を積む。
令和2年9月、大阪梅田に『西梅田シティクリニック』を開院。
「患者様ファースト」に徹底した医療マインドを持ち、内科診療にとどまらず健診センターや複数のクリニックを運営。
医療の敷居を下げ、忙しい方々にも医療アクセスを向上させることを使命とし、さまざまなプロジェクトに取り組む。
医院経営や医療関連のビジネスにも携わりつつ、医療現場に立ち続ける。
さらに、医師として医薬品の開発や海外での医療支援にも従事している。
- 公開日:2025/07/16
- 更新日:2025/07/16
クラウドドクターは24時間365日対応
現在の待ち時間
約3分

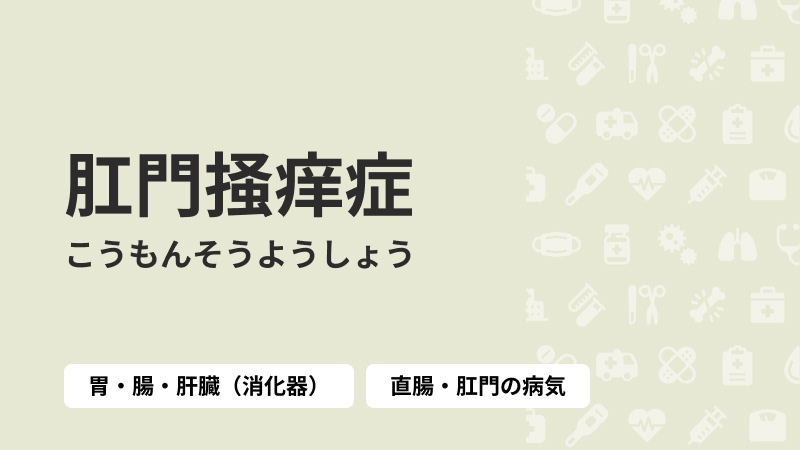
67.jpg)
65-1.jpg)
