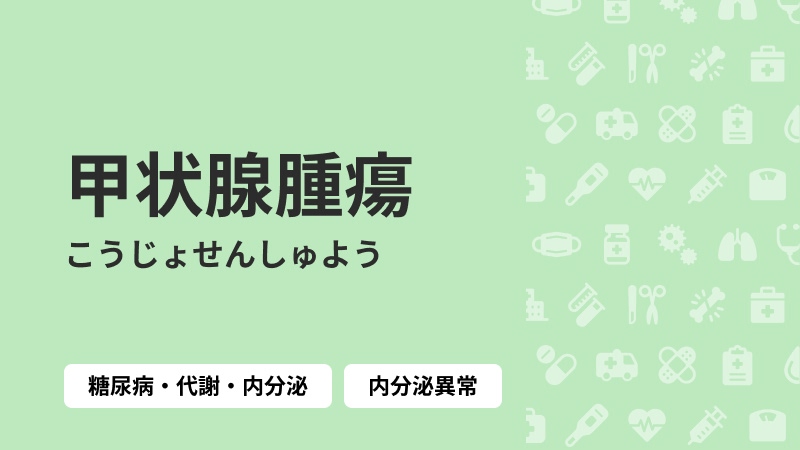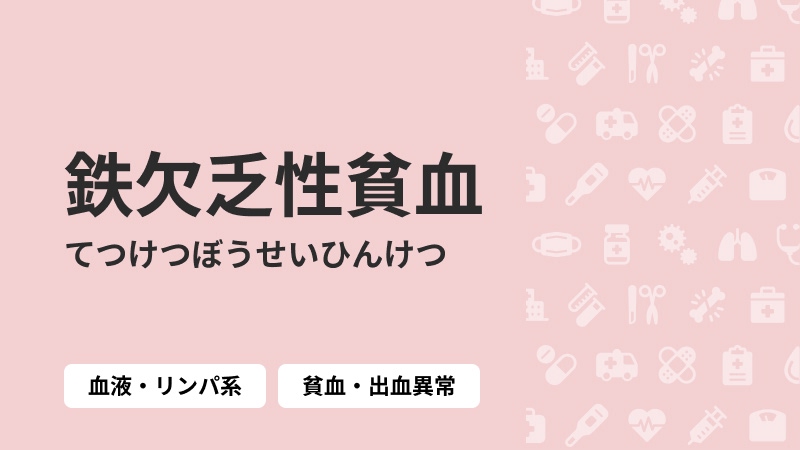脚気かっけ
脚気は、ビタミンB1の欠乏によって末梢神経や心臓の働きに障害が起こる病気です。しびれや歩行障害、むくみなどの症状が特徴で、重症例では心不全を起こすこともあります。早期のビタミン補給と原因対策が重要です。

脚気とは?
脚気(かっけ)とは、ビタミンB1(チアミン)の欠乏によって引き起こされる神経系および循環器系の障害を伴う疾患です。ビタミンB1は炭水化物の代謝に関与する重要な補酵素であり、不足するとエネルギー産生がうまくいかず、特に神経や心筋など高エネルギーを必要とする組織に影響を及ぼします。
脚気には主に二つの型があります。
- 神経型脚気:末梢神経障害を中心とした型で、しびれ、筋力低下、歩行困難が現れます
- 心臓型脚気(脚気心):心臓に影響が出て動悸、息切れ、浮腫などの心不全症状を呈します
かつて日本では白米中心の食事によるビタミンB1不足で脚気が多発しましたが、近年でも偏食やアルコール依存症、過度なダイエット、消化器疾患により再び注目されています。
原因
脚気の原因は、ビタミンB1の摂取不足または体内での利用障害です。ビタミンB1は体内に多く貯蔵されないため、数週間の欠乏でも症状が現れることがあります。
主な原因
- 白米やパンなど精製された炭水化物中心の食生活(ビタミンB1を含まない)
- 偏食:特に肉類や野菜、豆類の摂取不足
- 過度なダイエット:栄養バランスの崩れ
- アルコール多飲:吸収阻害や代謝促進によるビタミンB1の消費増加
- 胃や小腸の手術後:吸収不良
- 慢性下痢や吸収不良症候群:栄養素の取り込みが阻害される
- 妊娠・授乳期:ビタミン需要の増加
- 過度な運動やストレス:代謝亢進によるビタミン消費増加
現代では、外食中心やインスタント食品、清涼飲料の多飲といった生活習慣もリスク因子です。
症状
脚気の症状は神経系と循環器系に現れ、病状の進行に伴って多彩な症状を呈します。初期段階では見過ごされやすいため、早期発見が重要です。
神経型脚気の主な症状
- 手足のしびれ、灼熱感(とくに足底)
- 感覚鈍麻(触覚や振動覚が低下)
- 筋力低下(特に下肢)
- 歩行困難(ふらつき、つまずき)
- 反射低下または消失(膝蓋腱反射など)
- 倦怠感、集中力低下、記憶障害
心臓型脚気の主な症状
- 動悸、息切れ
- 下肢の浮腫(むくみ)
- 頸静脈怒張
- 肺うっ血による呼吸困難
- 血圧低下、頻脈
- 心不全によるショック(重症例)
ビタミンB1は神経伝達や心筋収縮にも関与しているため、進行すると生命に関わる症状に至ることもあります。
診断方法と治療方法
診断
- 問診:食事内容、アルコール摂取、既往歴(手術、消化器疾患など)
- 身体所見:神経症状、浮腫、心拍、反射異常の確認
- 血液検査:ビタミンB1濃度(チアミン濃度)の測定、乳酸・ピルビン酸濃度の上昇が補助所見
- 神経伝導検査:末梢神経の障害を評価
- 心エコー:心臓型脚気が疑われる場合、心機能評価を実施
- 画像検査(MRI):重度の神経障害がある場合の鑑別診断に有用
治療
- ビタミンB1の補充(内服または静脈投与)
- 軽症では内服、重症では点滴で迅速に補充 - 食事指導:ビタミンB1を多く含む食品(豚肉、豆類、玄米、野菜)を積極的に摂取
- 原因疾患の治療:吸収不良やアルコール依存の治療を並行して行う
神経症状は回復に時間を要しますが、心症状は早期に改善する傾向があります。
予後
脚気の予後は、ビタミンB1欠乏の重症度と治療開始の早さに大きく依存します。早期に治療が開始されれば、多くの場合は症状が改善し、後遺症を残さずに回復可能です。
予後が良好なケース
- 軽度の神経症状のみで、早期にビタミン補給が行われた
- 食事内容や生活習慣の改善ができた
- 心機能障害が軽度であった場合
予後が悪化しやすいケース
- 治療が遅れ、重度の心不全や神経障害を伴っていた場合
- アルコール依存や栄養障害が継続している場合
- 胃切除などで慢性的な吸収不良がある場合
とくに神経障害は回復までに数か月を要することがあり、完全に元通りにならないこともあります。
予防
脚気は予防可能な病気であり、栄養バランスの取れた食事が最大の対策です。特にビタミンB1を多く含む食品の積極的な摂取が推奨されます。
食生活での予防策
- 主食だけでなく、副菜・主菜をバランスよく摂取
- 玄米、雑穀米、全粒パンなど未精製穀類を取り入れる
- 豚肉、レバー、豆類、卵、野菜などのB1豊富な食材を食べる
- 加熱しすぎない(ビタミンB1は水溶性で熱に弱い)
生活習慣の工夫
- アルコールを控える(多量飲酒は吸収阻害の原因)
- 偏食や極端なダイエットを避ける
- ストレスや過労に注意する(B1の消費が増加)
- 高齢者や胃腸手術後の人は定期的な栄養評価を受ける
日々の習慣が脚気の発症予防につながります。
関連する病気や合併症
脚気は単なるビタミン欠乏症にとどまらず、全身にさまざまな合併症を引き起こすことがあります。これらの合併症を早期に見つけ、適切な管理を行うことが重要です。
関連する合併症・病態
- 心不全(脚気心):ビタミンB1不足により心筋が働かず、血液循環が障害される
- 末梢神経障害:足の感覚低下、麻痺、歩行障害など
- ウェルニッケ脳症:重度のB1欠乏により中枢神経系に障害が起こる(意識障害、眼球運動異常、運動失調など)
- コルサコフ症候群:記憶障害を主とする慢性脳症(ウェルニッケ脳症の後遺症)
- 食思不振症や重度のダイエットによる多発性神経炎
- アルコール性神経障害
これらの病態を避けるには、栄養状態の評価と早期対応が不可欠です。
症状が気になる場合や、体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。

クラウドドクターの
オンライン診療
クラウドドクターのオンライン診療
クラウドドクターでは、問診内容を元に全国から適したドクターがマッチングされ、あなたの診療を行います。診療からお薬の処方までビデオ通話で受けられるため、お忙しい方にもおすすめです。
-
24時間365日
いつでも診療OK -
保険診療が
ご利用可能 -
お近くの薬局やご自宅で
お薬の受取り可能
■ 参考・出典
厚生労働省e-ヘルスネット「ビタミンB1と脚気」(https://kennet.mhlw.go.jp/home)
日本内科学会「内科学 第11版」
日本ビタミン学会「脚気とビタミンB1」(https://www.vitamin-society.jp/)
国立国際医療研究センター「栄養関連疾患」(https://www.ncgm.go.jp/)
■ この記事を監修した医師

赤松 敬之医師 西梅田シティクリニック
近畿大学 医学部 卒
近畿大学医学部卒業。
済生会茨木病院にて内科・外科全般を担当。
その後、三木山陽病院にて消化器内科・糖尿病内科を中心に、内視鏡を含む内科全般にわたり研鑽を積む。
令和2年9月、大阪梅田に『西梅田シティクリニック』を開院。
「患者様ファースト」に徹底した医療マインドを持ち、内科診療にとどまらず健診センターや複数のクリニックを運営。
医療の敷居を下げ、忙しい方々にも医療アクセスを向上させることを使命とし、さまざまなプロジェクトに取り組む。
医院経営や医療関連のビジネスにも携わりつつ、医療現場に立ち続ける。
さらに、医師として医薬品の開発や海外での医療支援にも従事している。
- 公開日:2025/07/16
- 更新日:2025/07/16
クラウドドクターは24時間365日対応
現在の待ち時間
約3分