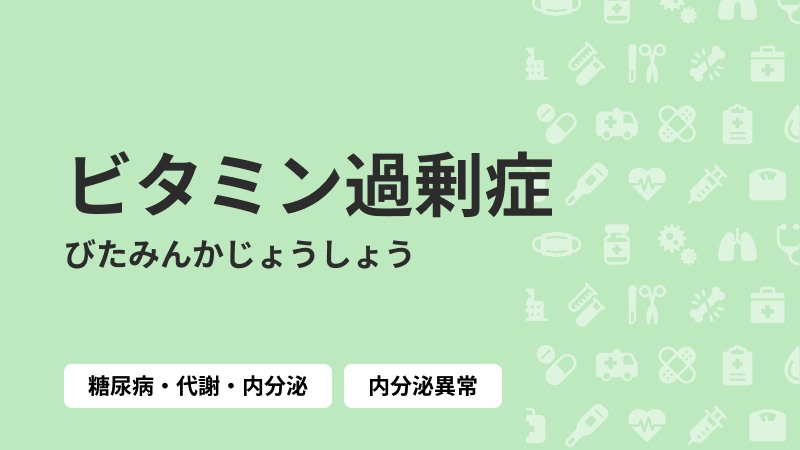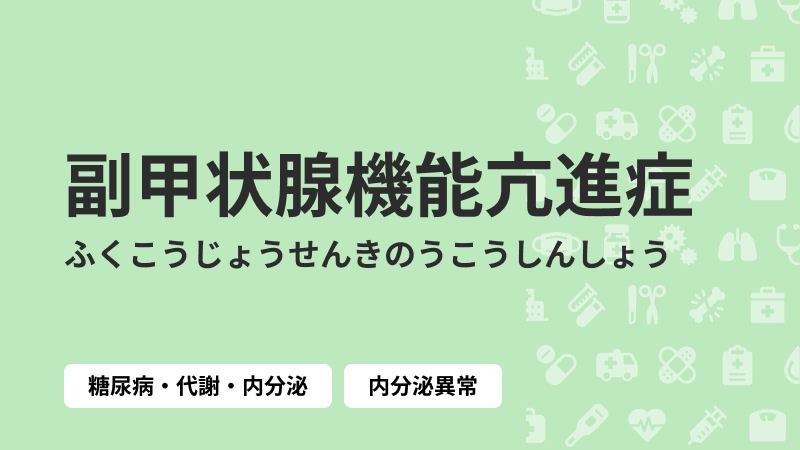ビタミン欠乏症びたみんけつぼうしょう
ビタミン欠乏症とは、体に必要なビタミンが不足し、さまざまな身体機能に障害が生じる状態です。ビタミンごとに特有の症状があり、食生活の乱れや吸収障害、過度なダイエットなどが主な原因です。早期の補充と原因への対処が重要です。

ビタミン欠乏症とは?
ビタミン欠乏症とは、体に必要なビタミンの摂取量が不足したり、吸収・代謝の異常によって、体内のビタミン濃度が低下し、さまざまな症状や疾患が現れる状態を指します。ビタミンは微量ながら生命活動に不可欠な栄養素であり、不足すると身体の代謝や免疫、神経、造血、骨形成などに異常をきたします。
ビタミンは水溶性と脂溶性に分類され、それぞれ不足した場合の症状や発症速度が異なります。特定のビタミンが欠乏することで、脚気、壊血病、夜盲症、貧血、神経障害などの古典的な病気が発症することがあります。現代では極端な偏食、過度のダイエット、アルコール依存症、吸収不良症候群、手術後の吸収障害などが原因で発症するケースが増えています。
日常的な食生活の見直しと、必要に応じた医療的な補充が重要です。
原因
ビタミン欠乏症の原因は多岐にわたり、主に摂取不足、吸収障害、代謝異常、排泄過剰が挙げられます。加齢や疾患、ライフスタイルの変化によって発症リスクが高まることもあります。
主な原因
- 偏食:特定の食品に偏った食生活
- 過度なダイエット:エネルギーや栄養素の摂取不足
- アルコール多飲:ビタミンB群の消費増加や吸収障害
- 高齢者:食事量の減少、吸収能力の低下
- 消化器疾患:胃切除後、吸収不良症候群、炎症性腸疾患など
- 薬剤の影響:抗てんかん薬、抗結核薬、メトトレキサートなどによる代謝障害
- 妊娠・授乳:ビタミンの需要が増加する
- 慢性疾患やストレス:ビタミン消費量の増加
特定のビタミンだけが不足する場合もあれば、複数のビタミンが同時に欠乏することもあり、原因の特定と早期の対応が重要です。
症状
ビタミンごとに特有の症状が現れますが、全身にさまざまな影響を及ぼします。欠乏状態が続くと慢性的な体調不良や生活の質の低下、場合によっては命に関わることもあります。
代表的なビタミンと症状
- ビタミンA欠乏:夜盲症(暗い所で見えにくくなる)、皮膚の乾燥、感染症への抵抗力低下
- ビタミンB1欠乏:脚気(手足のしびれ、筋力低下、心不全)
- ビタミンB2欠乏:口角炎、舌炎、皮膚炎
- ビタミンB6欠乏:末梢神経障害、うつ症状
- ビタミンB12欠乏:巨赤芽球性貧血、しびれ、記憶力低下
- 葉酸欠乏:貧血、胎児の神経管閉鎖障害(妊娠中)
- ビタミンC欠乏:壊血病(出血傾向、歯肉炎、倦怠感)
- ビタミンD欠乏:骨軟化症、骨粗鬆症、筋力低下
- ビタミンK欠乏:出血傾向(血液が止まりにくい)
複数の症状が重なる場合には、医療機関での評価が必要です。
診断方法と治療方法
診断
- 問診:食生活、体調、生活習慣、既往歴や服薬歴を確認
- 身体診察:皮膚や粘膜の異常、神経症状、体重減少などを観察
- 血液検査
- ビタミン濃度の測定(例:ビタミンB12、葉酸、ビタミンD)
- 間接的所見(貧血、CRP、電解質異常など) - 尿検査:水溶性ビタミンの排泄状況
- 必要に応じて画像検査(骨密度検査など)
治療
- 食事療法
- 欠乏しているビタミンを多く含む食品を意識的に摂取
- 管理栄養士の指導によるバランスの取れた食事の再構築 - サプリメントや医薬品による補充
- 経口または注射による補充(例:ビタミンB12筋注、ビタミンD内服)
- 欠乏の重症度や吸収障害の有無に応じて投与法を選択 - 原因疾患の治療:吸収障害や薬剤性であればその治療も並行して行う
再発防止のためには、長期的な生活改善も必要です。
予後
ビタミン欠乏症の予後は、欠乏の種類や重症度、補充のタイミングに大きく左右されます。早期に原因を特定し、適切な補充を行えば、多くのケースで回復が見込めます。
予後が良好な場合
- 軽度の欠乏で早期に補充を開始できた
- 一時的な食事の乱れやダイエットによるもので、生活改善ができた
- 定期的なフォローアップが行われている
予後が悪化する可能性があるケース
- 長期間にわたる欠乏(慢性アルコール依存症、吸収不良症候群など)
- 神経系の障害(ビタミンB1やB12)は、補充しても回復が限定的なことがある
- 高齢者や基礎疾患のある人では、再発リスクが高い
- 妊娠中の葉酸欠乏では胎児への影響もある
再発予防には生活環境の整備と食生活の継続的な改善が重要です。
予防
ビタミン欠乏症は、日常生活の中で予防が可能な病態です。偏りのない食事と、健康状態に応じた栄養管理が大切です。
食生活の工夫
- 多品目をバランスよく摂取:主食・主菜・副菜を基本に
- 加工食品やファストフード中心の食事を避ける
- 野菜・果物を1日350g以上目安に摂取
- 乳製品、魚、豆類、卵なども適度に取り入れる
- 日光にあたる習慣(ビタミンD合成のため)
その他の予防策
- 過度なダイエットを避ける
- アルコールの摂取は適量に
- 妊娠中や授乳中は、医師の指導のもと必要なサプリメントを摂取
- 高齢者や疾患を持つ人は定期的な栄養評価を行う
個人の状態に応じて、栄養指導やサプリメントの活用が効果的です。
関連する病気や合併症
ビタミン欠乏症は、他の疾患の一因となったり、既存の病気を悪化させる要因にもなります。慢性化すると全身に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
関連する疾患・合併症
- 神経障害(ビタミンB1・B12・葉酸):末梢神経障害、認知機能障害
- 貧血(ビタミンB12・葉酸・ビタミンC):巨赤芽球性貧血、鉄吸収障害
- 骨疾患(ビタミンD・K):骨粗鬆症、骨軟化症、易骨折性
- 皮膚・粘膜の異常(ビタミンB群・A):皮膚炎、口内炎、口角炎
- 免疫機能低下(ビタミンA・C・D):感染症にかかりやすくなる
- 血液凝固異常(ビタミンK):出血しやすくなる
- 眼科疾患(ビタミンA):夜盲症、視力障害
これらを予防するためにも、ビタミン欠乏の早期発見と対応が不可欠です。
症状が気になる場合や、体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。

クラウドドクターの
オンライン診療
クラウドドクターのオンライン診療
クラウドドクターでは、問診内容を元に全国から適したドクターがマッチングされ、あなたの診療を行います。診療からお薬の処方までビデオ通話で受けられるため、お忙しい方にもおすすめです。
-
24時間365日
いつでも診療OK -
保険診療が
ご利用可能 -
お近くの薬局やご自宅で
お薬の受取り可能
■ 参考・出典
厚生労働省e-ヘルスネット「ビタミンと健康」(https://kennet.mhlw.go.jp/home)
日本臨床栄養学会「ビタミン欠乏症とその予防」(https://www.jcna.jp/)
国立国際医療研究センター「栄養と代謝」(https://www.ncgm.go.jp/)
日本内科学会「内科学 第11版」
■ この記事を監修した医師

赤松 敬之医師 西梅田シティクリニック
近畿大学 医学部 卒
近畿大学医学部卒業。
済生会茨木病院にて内科・外科全般を担当。
その後、三木山陽病院にて消化器内科・糖尿病内科を中心に、内視鏡を含む内科全般にわたり研鑽を積む。
令和2年9月、大阪梅田に『西梅田シティクリニック』を開院。
「患者様ファースト」に徹底した医療マインドを持ち、内科診療にとどまらず健診センターや複数のクリニックを運営。
医療の敷居を下げ、忙しい方々にも医療アクセスを向上させることを使命とし、さまざまなプロジェクトに取り組む。
医院経営や医療関連のビジネスにも携わりつつ、医療現場に立ち続ける。
さらに、医師として医薬品の開発や海外での医療支援にも従事している。
- 公開日:2025/07/16
- 更新日:2026/02/19
クラウドドクターは24時間365日対応
現在の待ち時間
約3分