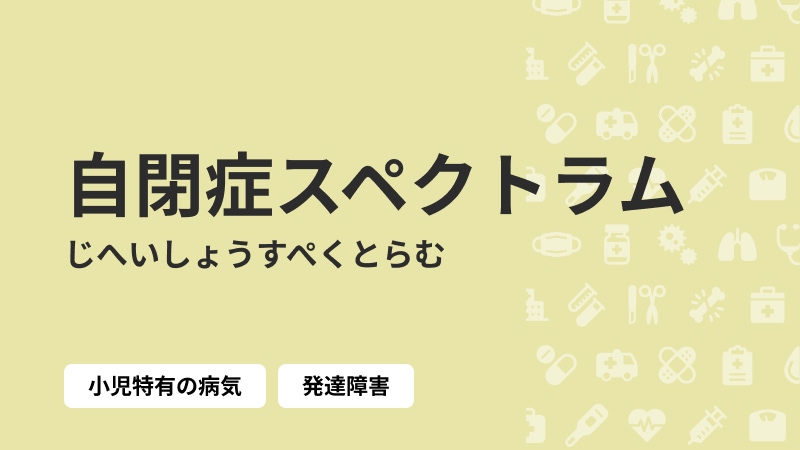注意欠陥・多動性障害(ADHD)ちゅういけっかん・たどうせいしょうがい
注意欠陥・多動性障害(ADHD)は、不注意、多動性、衝動性といった特徴が見られる発達障害のひとつです。子どもだけでなく大人にも症状が続くことがあり、日常生活や社会生活に支障をきたす場合には診断と支援が重要になります。
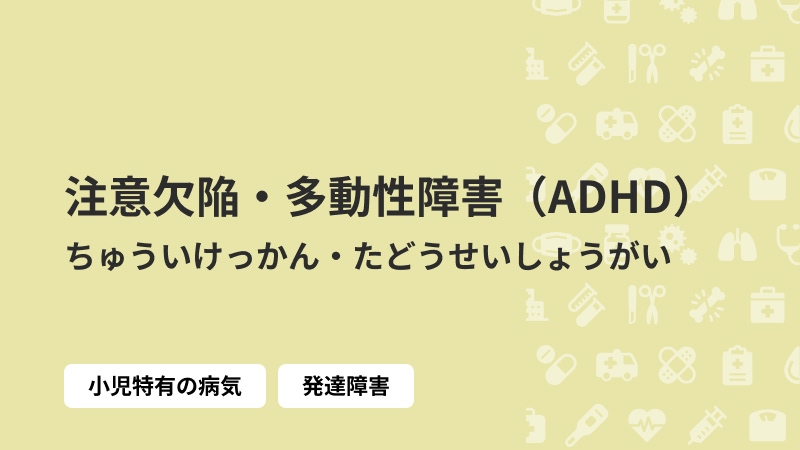
注意欠陥・多動性障害(ADHD)とは?
注意欠陥・多動性障害(ADHD:Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder)は、発達障害の一種であり、主に「不注意」「多動性」「衝動性」といった行動特性がみられる神経発達症のひとつです。脳の発達や機能に関連する特性によって、注意の持続が難しい、じっとしていられない、衝動的に行動してしまうなどの症状が現れます。
ADHDは小児期に発症し、学童期に学校生活や家庭生活で困難を抱えることがありますが、大人になっても症状が残ることも多く、現在では「成人のADHD」としての認識も高まっています。本人の努力不足ではなく、脳の情報処理の仕方に由来するものであり、医療や教育、社会的な支援が重要となります。
原因
ADHDの正確な原因は解明されていませんが、複数の要因が関係すると考えられています。特に脳の前頭葉を中心とした神経伝達物質(ドーパミンやノルアドレナリン)の働きの異常が、注意や衝動のコントロールに影響しているとされます。
主な原因や関連要因
- 脳の機能的・構造的異常(特に前頭前野、線条体など)
- 神経伝達物質の不均衡(ドーパミン、ノルアドレナリンの調整異常)
- 遺伝的素因:家族内でADHDを持つ人がいる割合が高い
- 出生前・出生後の環境因子(低出生体重、早産、喫煙・飲酒などの母体環境)
- その他:栄養状態、脳損傷、鉛などの有害物質曝露の可能性
これらの要因が複雑に関係しており、ADHDは「親の育て方」や「性格」の問題ではありません。理解と支援の姿勢が求められます。
症状
ADHDの症状は、大きく「不注意」「多動性」「衝動性」の3つの特性に分類されます。これらのうち1つだけが目立つ場合もあれば、複数が重なって現れることもあります。
不注意
- 集中力が続かない
- 気が散りやすい
- 忘れ物や失くし物が多い
- 話を聞いていないように見える
- 作業の段取りや整理整頓が苦手
多動性
- 座っていられず体を動かし続ける
- 静かにしていることができない
- しゃべりすぎる
- 状況に合わない行動が目立つ
衝動性
- 順番を待てない
- 人の話をさえぎってしまう
- 思いつきで行動してしまう
- 感情のコントロールが難しい
年齢によって現れ方は異なり、子どもでは落ち着きのなさ、大人では段取りの悪さやうっかりミスなどが目立つことがあります。
診断方法と治療方法
診断
ADHDの診断は、症状の観察と問診、行動評価を中心に行われます。子どもの場合は保護者や教師からの情報も参考にします。
- 問診と行動観察:生活全般での様子、支障の程度などを確認
- 診断基準:DSM-5(アメリカ精神医学会)やICD-10などを用いる
- 発達歴の確認:幼少期からの症状の持続性を評価
- 心理検査(必要に応じて):知能検査、注意機能検査など
- スクリーニング尺度:ADHD-RSやConners尺度などの評価票
治療
ADHDの治療は、薬物療法と行動療法を中心とした総合的な支援が基本です。
- 薬物療法:中枢神経刺激薬(メチルフェニデート製剤など)、非刺激薬(アトモキセチンなど)
- 環境調整:学校や職場での配慮、支援制度の活用
- 行動療法・認知行動療法:自己管理スキルや問題解決力の向上
- 親や教師への支援:ペアレントトレーニングや教育的支援
症状に応じた個別対応が重要であり、成長や環境に合わせた継続的な支援が求められます。
予後
ADHDは慢性的な特性ですが、適切な支援や治療を受けることで日常生活における支障を大きく軽減することができます。年齢とともに症状の現れ方は変化し、大人になると多動性が落ち着き、不注意が主となることが多いです。
予後が良好なケース
- 早期に診断され、適切な治療と支援を受けられた場合
- 家族や教育機関による理解と協力がある場合
- 本人が自分の特性を理解し、対処法を身につけられた場合
注意が必要なケース
- 周囲の理解が得られず自己否定感が強くなる
- 学業や就労における失敗経験が多く、二次障害(不登校、うつ、不安など)を併発する
- 本人が支援を拒否することで生活に困難が蓄積される
ADHDは一人ひとり特性が異なるため、個別性を重視した対応が予後に大きく影響します。
予防
ADHDは先天的な神経発達の特性によるものであり、予防することはできません。しかし、早期に特性を見極め、生活環境を整えることで症状の悪化や二次的な問題を防ぐことができます。
予防的支援のポイント
- 幼児期からの発達の観察と記録
- 保育園・学校と連携し、早期に困りごとを共有
- 過剰な叱責ではなく、行動の意味を理解し対話を重ねる
- 子ども自身の強みに目を向ける関わり方
- ストレスや疲労をため込まない生活習慣の確立
- 必要に応じて医療機関に早めに相談する
特性に合った対応をすることで、本人の自己肯定感を高め、生活上の困難を最小限に抑えることが可能になります。
関連する病気や合併症
ADHDは単独で存在することもありますが、他の発達障害や精神疾患と合併しやすいことが知られています。これらの合併症は生活への影響を大きくするため、総合的な支援が必要です。
関連疾患・合併症
- 学習障害(LD):読み書きや計算に困難を伴うことがある
- 自閉スペクトラム症(ASD):社会性やこだわりの強さなどが重なるケースもある
- 反抗挑戦性障害(ODD):指示への反発や強い怒りの爆発など
- 不安障害、うつ病:自己評価の低さや失敗体験から発症することがある
- 睡眠障害:入眠困難、中途覚醒、日中の眠気など
ADHDに加えてこれらの症状がみられる場合は、医師と相談しながら包括的な支援を検討することが重要です。
症状が気になる場合や、体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。

クラウドドクターの
オンライン診療
クラウドドクターのオンライン診療
クラウドドクターでは、問診内容を元に全国から適したドクターがマッチングされ、あなたの診療を行います。診療からお薬の処方までビデオ通話で受けられるため、お忙しい方にもおすすめです。
-
24時間365日
いつでも診療OK -
保険診療が
ご利用可能 -
お近くの薬局やご自宅で
お薬の受取り可能
■ 参考・出典
厚生労働省 e-ヘルスネット(https://kennet.mhlw.go.jp/home)
日本小児神経学会(https://www.childneuro.jp/)
日本児童青年精神医学会(https://child-adolesc.jp/)
日本発達障害ネットワーク(https://jddnet.jp/)
国立精神・神経医療研究センター(https://www.ncnp.go.jp/)
■ この記事を監修した医師

鄭 賢樹医師 てい小児科クリニック
近畿大学 医学部 卒
守口敬仁会病院で消化器外科医として研鑽を積んだのち、りんくう総合医療センター救命診療科で外傷・集中治療に従事。在宅医療専門クリニック「グリーングラス」では訪問診療に携わり、大手美容皮膚科・医療痩身クリニックでは美容医療の経験も重ねてきた。急性期医療から慢性疾患管理、美容領域、さらには在宅医療に至るまで、幅広い分野を経験。
2024年より「てい小児科クリニック」に赴任。小児科を長年支えてきた父の志を受け継ぎながら、内科、美容皮膚科、医療痩身、訪問診療を新たに導入し、地域に寄り添う“人生まるごと”の医療を提供することを目指している。
モットーは「医療を介して地域と絆でつながる」こと。
そして、「患者さま以上に、患者さまの健康を想う」こと。
日々の診療の中で、「今日も、あなたの“これから”を支えたい」という想いを胸に、子どもから高齢者まで、すべての世代の健康を全力で支える医療に取り組んでいる。
- 公開日:2025/09/19
- 更新日:2025/09/19
クラウドドクターは24時間365日対応
現在の待ち時間
約3分