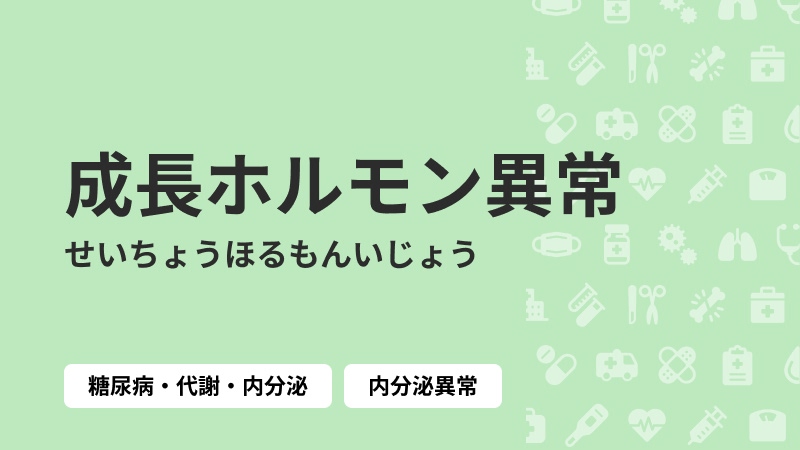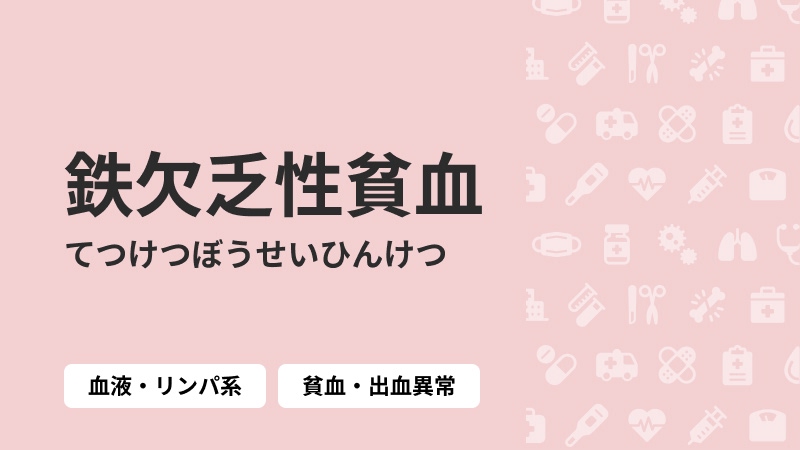小児肥満しょうにひまん
小児肥満は、成長期の子どもにおいて体脂肪が過剰に蓄積された状態を指します。生活習慣の影響が大きく、将来的な生活習慣病や心理的問題のリスクを高めるため、早期の介入と家庭・学校での一体的な対策が重要です。

小児肥満とは?
小児肥満とは、18歳未満の子どもにおいて体脂肪が過剰に蓄積された状態を指します。肥満の評価は成人と異なり、身長・体重・年齢・性別をもとに計算される「肥満度」によって判定されます。日本では、肥満度が20%以上の場合を肥満と定義しています。
小児期の肥満は、単なる「体格の良さ」とは異なり、内臓脂肪の増加によって将来の生活習慣病(高血圧、脂質異常症、2型糖尿病など)や整形外科的障害、精神的問題のリスクを高めます。特に学童期から思春期にかけての肥満は、大人になっても肥満が持続しやすく、「肥満の固定化」と呼ばれる状態に移行しやすいとされています。
早期発見と対策によって、健康への影響を未然に防ぐことが可能です。
原因
小児肥満の原因は、大きく分けて生活習慣によるものと、病気や体質によるものに分類されます。ほとんどの小児肥満は生活習慣に起因する「単純性肥満」であり、日常の行動や家庭環境と密接に関係しています。
主な原因
- 過食:高カロリー・高脂質の食品を過剰に摂取
- 偏食:野菜や魚が少なく、炭水化物やお菓子中心の食事
- 運動不足:外遊びやスポーツの機会が少ない
- 間食や夜食の習慣
- 長時間のテレビ・ゲーム・スマートフォンの使用
- 家族の肥満(遺伝的要因と生活習慣の影響の両方)
- 乳児期の体重増加(肥満リスクの増加因子)
病的原因(まれ)
- ホルモン異常(クッシング症候群、甲状腺機能低下症など)
- 遺伝子異常や先天性疾患(例:プラダー・ウィリ症候群)
多くの子どもは日常生活の中で肥満傾向を強めており、家庭全体での対応が不可欠です。
症状
小児肥満は見た目の変化だけでなく、身体的・心理的・社会的な症状としてさまざまな影響を及ぼします。初期には目立った症状がなくても、体重の増加に伴って健康に影響を及ぼすようになります。
身体的な症状
- BMIの増加、腹囲の肥大
- 息切れ、疲れやすさ
- いびき、睡眠時無呼吸症候群
- 皮膚のただれ、あせも、黒ずみ(黒色表皮腫)
- 月経不順(女子)
- 関節や足への負担(扁平足、膝関節症など)
精神的・行動面の症状
- 集中力の低下、学力の低下
- いじめやからかいへの不安
- 自己肯定感の低下、うつ傾向
- 人前での行動の萎縮
将来の健康への影響
脂質異常症、耐糖能異常、インスリン抵抗性などが学童期から始まる
症状が進行すると日常生活や学業、社会活動に支障をきたすこともあります。
診断方法と治療方法
診断
- 肥満度の計算
- 肥満度(%)={(実測体重-標準体重)÷標準体重}×100
- 肥満度が20%以上で肥満、30%以上で高度肥満と判定される - 身体測定:身長、体重、腹囲
- 問診:食事内容、運動習慣、家庭環境など
- 血液検査:脂質、血糖、肝機能、インスリン抵抗性の評価
- 睡眠や心理面の評価も必要に応じて実施
治療
- 生活習慣の見直しが基本
- 食事療法
・栄養バランスの取れた食事
・食べ過ぎ・間食・外食を控える
- 運動療法
・毎日1時間程度の身体活動(外遊び、運動)を推奨
- 行動療法
・生活記録や体重の記録、目標設定を活用
・家族全体での取り組み - 薬物療法や手術は極めて限定的な例でのみ実施されます
小児肥満は本人だけでなく家庭・地域が一体となって取り組む必要があります。
予後
小児肥満の予後は、早期に介入できたかどうかが大きく影響します。放置すると思春期以降も肥満が続き、生活習慣病や心血管疾患のリスクが高まります。
予後が良好な場合
- 学童期までに肥満の改善ができた
- 家族での協力体制が整っている
- 食事・運動習慣の定着ができている
- 心理的サポートが受けられている
予後が悪化するリスク
- 思春期以降も肥満が持続している
- 脂質異常症、2型糖尿病、高血圧などがすでに発症している
- 心理的要因(ストレス、うつ、摂食障害)への対応が不十分
- 社会的支援(学校・地域)に乏しい環境
一度改善したように見えてもリバウンドすることがあるため、長期的な支援と継続的なフォローが必要です。
予防
小児肥満は予防可能な疾患であり、日常の生活習慣の積み重ねが最も重要です。家庭、学校、地域社会が連携して、健康的な生活環境を整えることが鍵となります。
食生活での予防
- 1日3食を規則正しく摂る
- 野菜や魚を積極的に取り入れ、加工食品・ジュースを減らす
- よく噛んでゆっくり食べる
- 間食は決まった時間・量に限定する
- 夜食や食べ過ぎを避ける
運動習慣の定着
- 毎日の通学、遊びの中で体を動かす機会をつくる
- テレビやゲーム時間を1日2時間以内に抑える
- スポーツや部活動への参加を促す
生活環境の整備
- 十分な睡眠(小学生は9〜11時間が目安)
- ストレス対策や家庭内コミュニケーションの充実
- 学校での保健指導や給食を通じた食育
予防は幼少期からの継続的な取り組みが必要です。
関連する病気や合併症
小児肥満は、成長期であるにもかかわらず、成人と同様の生活習慣病やその他の合併症を引き起こす可能性があります。身体的・精神的・社会的な問題が複雑に絡み合います。
主な身体的合併症
- 2型糖尿病
- 脂質異常症
- 高血圧
- 非アルコール性脂肪肝(NAFLD)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 整形外科的疾患(膝関節症、成長痛)
精神・行動面での合併症
- 自尊心の低下
- いじめ、登校拒否
- うつ症状、摂食障害
将来的な影響
- 成人期のメタボリックシンドローム、心筋梗塞、脳卒中のリスク増加
- 経済的負担や社会的困難の増加
小児期における肥満の予防と対策は、生涯の健康維持に直結する重要な課題です。
症状が気になる場合や、体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。

クラウドドクターの
オンライン診療
クラウドドクターのオンライン診療
クラウドドクターでは、問診内容を元に全国から適したドクターがマッチングされ、あなたの診療を行います。診療からお薬の処方までビデオ通話で受けられるため、お忙しい方にもおすすめです。
-
24時間365日
いつでも診療OK -
保険診療が
ご利用可能 -
お近くの薬局やご自宅で
お薬の受取り可能
■ 参考・出典
厚生労働省e-ヘルスネット「小児肥満」(https://kennet.mhlw.go.jp/home)
日本小児内分泌学会「小児肥満症の診療ガイドライン」(https://www.jspe.jp/)
国立成育医療研究センター「こどもの肥満とその対策」(https://www.ncchd.go.jp/)
日本内科学会「内科学 第11版」
■ この記事を監修した医師

鄭 賢樹医師 てい小児科クリニック
近畿大学 医学部 卒
守口敬仁会病院で消化器外科医として研鑽を積んだのち、りんくう総合医療センター救命診療科で外傷・集中治療に従事。在宅医療専門クリニック「グリーングラス」では訪問診療に携わり、大手美容皮膚科・医療痩身クリニックでは美容医療の経験も重ねてきた。急性期医療から慢性疾患管理、美容領域、さらには在宅医療に至るまで、幅広い分野を経験。
2024年より「てい小児科クリニック」に赴任。小児科を長年支えてきた父の志を受け継ぎながら、内科、美容皮膚科、医療痩身、訪問診療を新たに導入し、地域に寄り添う“人生まるごと”の医療を提供することを目指している。
モットーは「医療を介して地域と絆でつながる」こと。
そして、「患者さま以上に、患者さまの健康を想う」こと。
日々の診療の中で、「今日も、あなたの“これから”を支えたい」という想いを胸に、子どもから高齢者まで、すべての世代の健康を全力で支える医療に取り組んでいる。
- 公開日:2025/07/16
- 更新日:2025/09/19
クラウドドクターは24時間365日対応
現在の待ち時間
約3分