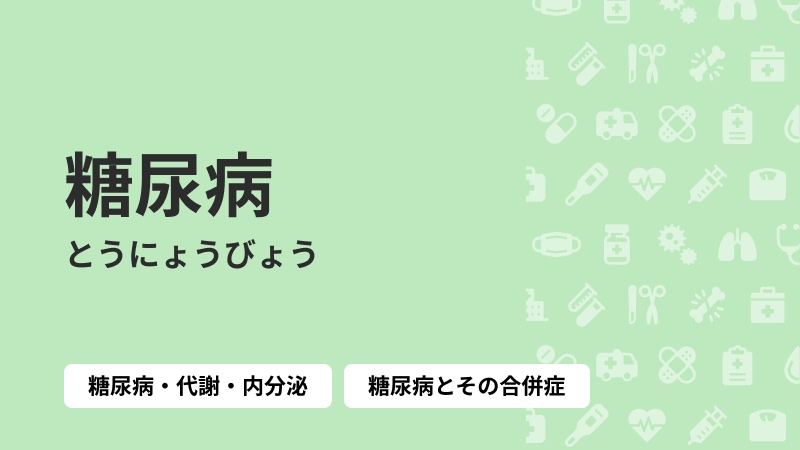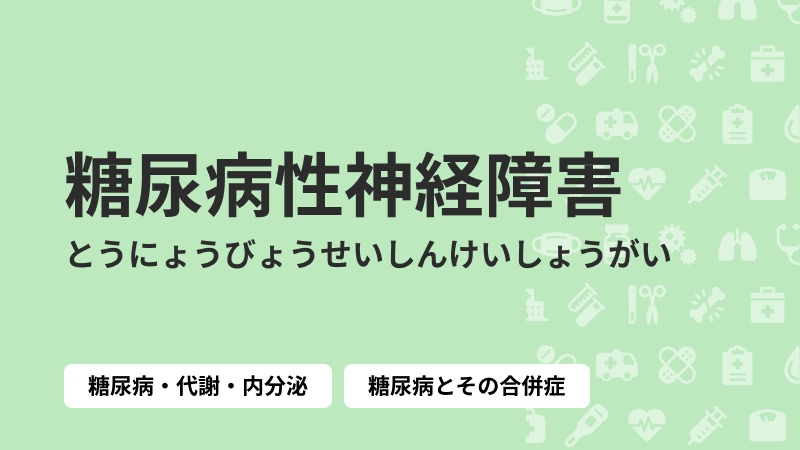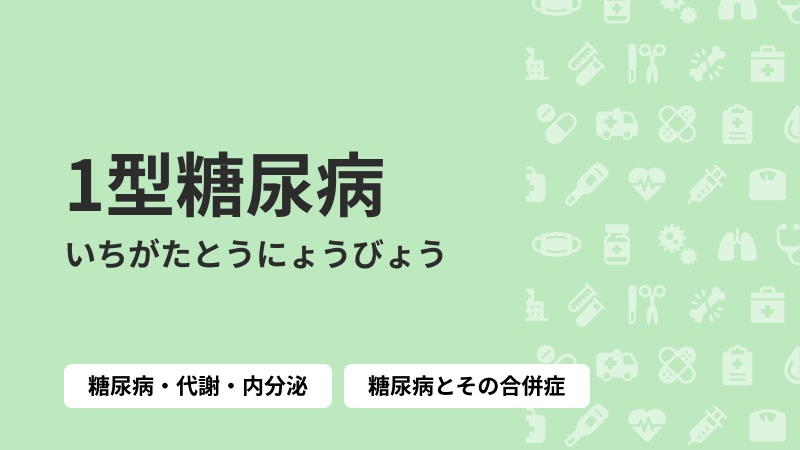2型糖尿病にがたとうにょうびょう
2型糖尿病は、インスリンの分泌不足や効きにくさによって血糖値が慢性的に高くなる病気です。生活習慣との関連が強く、初期は無症状でも放置すると合併症を引き起こします。食事や運動などの生活習慣改善と薬物療法での血糖管理が重要です。
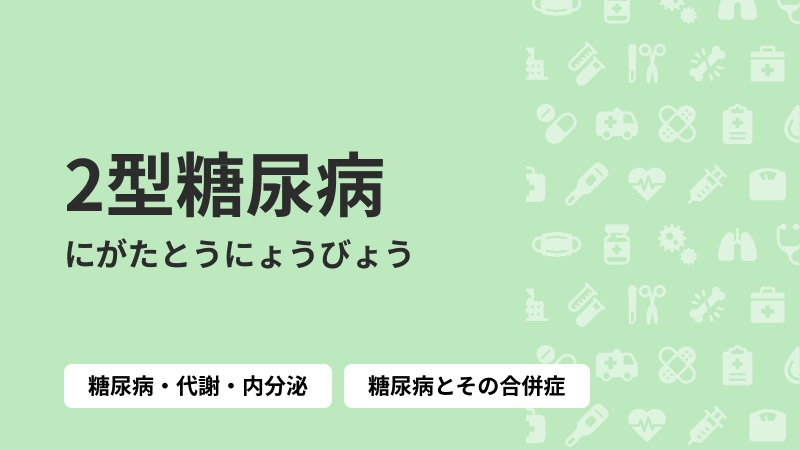
2型糖尿病とは?
2型糖尿病とは、インスリンの分泌量が不足したり、体内でインスリンがうまく働かなくなったりすることで、血糖値が慢性的に高くなる病気です。糖尿病全体の90%以上を占める最も一般的なタイプで、主に中高年に多く発症しますが、近年では若年層にも増えています。
インスリンは膵臓から分泌され、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませる働きがあります。2型糖尿病ではこのインスリンの「分泌不足」または「インスリン抵抗性(効きにくくなる)」が起こり、血糖値が下がりにくくなります。
高血糖状態が続くと、さまざまな合併症(眼、腎臓、神経、血管など)が進行し、生活の質が低下するため、早期の診断と治療介入が重要です。
原因
2型糖尿病は遺伝的素因と生活習慣の影響が複合して発症します。特に食べ過ぎや運動不足、肥満といった生活習慣は発症リスクを大きく高めます。
主な原因・危険因子
- 遺伝的要因:家族に糖尿病の人がいると発症しやすい
- 加齢:40歳以降で発症率が上昇する
- 肥満:特に内臓脂肪型肥満がインスリン抵抗性を高める
- 運動不足:筋肉でのブドウ糖利用が低下し、血糖値が上がりやすくなる
- 高脂肪・高糖質の食生活:膵臓への負担が増加
- ストレスや睡眠不足:ホルモンバランスが崩れ、血糖上昇を促す
- 喫煙:インスリンの効きが悪くなり、血管にも悪影響を及ぼす
これらの要因が重なることで、膵臓の機能が低下し、発症に至ります。
症状
2型糖尿病の初期はほとんど無症状のことが多く、健康診断で指摘されるまで気づかないケースも少なくありません。症状が出る頃には高血糖状態が長く続いていることが多いため、注意が必要です。
高血糖による主な症状
- のどの渇き、口渇感
- 頻尿
- 疲れやすさ、倦怠感
- 体重減少(食欲があるのにやせる)
- 視力低下、かすみ目
- 皮膚のかゆみ、感染症(とびひ、膀胱炎など)
- 手足のしびれや感覚異常
- 傷や口内炎が治りにくい
- 陰部のかぶれやただれ(女性ではカンジダ感染など)
進行した場合の症状
- 糖尿病性ケトアシドーシス(まれ):吐き気、嘔吐、意識障害など
症状に気づいたときには合併症が進行していることもあるため、早期発見が重要です。
診断方法と治療方法
診断
- 血糖値の測定
- 空腹時血糖値が126mg/dL以上
- 随時血糖値が200mg/dL以上
- 75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)で2時間値が200mg/dL以上 - HbA1cの測定:過去1〜2か月の血糖コントロール状態を反映(6.5%以上で糖尿病の可能性)
- 尿検査:尿糖、尿タンパク、尿ケトン体の確認
- その他:合併症の有無を調べる検査(眼底検査、腎機能、末梢神経など)
治療
- 食事療法
- 栄養バランスの良い食事、カロリー・糖質制限、食物繊維摂取の推奨 - 運動療法
- 有酸素運動(ウォーキング、サイクリングなど)を週150分程度推奨 - 薬物療法
- 経口血糖降下薬(メトホルミン、DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬など)
- インスリン療法(効果が不十分な場合)
治療は個々の病態に応じて組み合わせて進められます。
予後
2型糖尿病の予後は、血糖コントロールの程度と合併症の有無により大きく異なります。早期に発見され、適切な治療を受けていれば、健康な人と同様の生活を送ることが可能です。
良好な予後が見込める条件
- 定期的な通院と血糖・HbA1cの管理ができている
- 生活習慣の改善(食事、運動)を継続できている
- 合併症が発症していない、または初期で抑えられている
- 体重や血圧、脂質などの管理も良好
予後が悪化するケース
- 血糖値が常に高値で推移している
- 腎症、網膜症、神経障害などの合併症が進行
- 心筋梗塞や脳梗塞など大血管合併症が発症した場合
適切な管理を継続することで、予後を大きく改善できます。
予防
2型糖尿病は予防が可能な疾患であり、特に生活習慣の改善が最も効果的な対策です。発症前の「予備群」の段階で介入すれば、多くの場合、糖尿病を回避できます。
予防のための生活習慣
- バランスの良い食事:糖質・脂質の摂りすぎに注意し、野菜を積極的に摂取
- 適正体重の維持:BMI25未満が目安
- 定期的な運動習慣:週150分以上の中強度の運動が推奨される
- 禁煙:喫煙はインスリン抵抗性を悪化させる
- 過度の飲酒を避ける
定期的な検診
- 健康診断で血糖値やHbA1cを確認
- 予備群(境界型)と診断された場合は早めの対応を
家族に糖尿病患者がいる人や肥満傾向のある人は特に注意が必要です。
関連する病気や合併症
2型糖尿病は長期にわたって高血糖が続くことで、全身の血管や神経にさまざまな合併症を引き起こします。これらを予防・抑制するためには、血糖コントロールと定期的な検査が重要です。
細小血管障害
- 糖尿病網膜症:視力障害や失明の原因に
- 糖尿病腎症:尿タンパクの出現から始まり、最終的には透析が必要となることも
- 糖尿病神経障害:手足のしびれ、自律神経症状(便秘、頻尿など)を起こす
大血管障害
- 心筋梗塞・狭心症
- 脳梗塞・脳出血
- 末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)
その他
- 歯周病、感染症への抵抗力低下
- 認知機能低下(血糖変動との関連)
- 脂質異常症、高血圧などとの合併
これらの合併症は日常生活に大きな支障をきたすため、早期予防が鍵となります。
症状が気になる場合や、体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。

クラウドドクターの
オンライン診療
クラウドドクターのオンライン診療
クラウドドクターでは、問診内容を元に全国から適したドクターがマッチングされ、あなたの診療を行います。診療からお薬の処方までビデオ通話で受けられるため、お忙しい方にもおすすめです。
-
24時間365日
いつでも診療OK -
保険診療が
ご利用可能 -
お近くの薬局やご自宅で
お薬の受取り可能
■ 参考・出典
日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン」(https://www.jds.or.jp/)
厚生労働省e-ヘルスネット「2型糖尿病」(https://kennet.mhlw.go.jp/home)
国立国際医療研究センター「糖尿病の管理と予防」(https://www.ncgm.go.jp/)
日本内科学会「内科学書 第11版」
日本動脈硬化学会「生活習慣病と動脈硬化」(https://www.j-athero.org/jp/)
■ この記事を監修した医師

赤松 敬之医師 西梅田シティクリニック
近畿大学 医学部 卒
近畿大学医学部卒業。
済生会茨木病院にて内科・外科全般を担当。
その後、三木山陽病院にて消化器内科・糖尿病内科を中心に、内視鏡を含む内科全般にわたり研鑽を積む。
令和2年9月、大阪梅田に『西梅田シティクリニック』を開院。
「患者様ファースト」に徹底した医療マインドを持ち、内科診療にとどまらず健診センターや複数のクリニックを運営。
医療の敷居を下げ、忙しい方々にも医療アクセスを向上させることを使命とし、さまざまなプロジェクトに取り組む。
医院経営や医療関連のビジネスにも携わりつつ、医療現場に立ち続ける。
さらに、医師として医薬品の開発や海外での医療支援にも従事している。
- 公開日:2025/07/16
- 更新日:2026/02/19
クラウドドクターは24時間365日対応
現在の待ち時間
約3分