高血圧こうけつあつ
高血圧(Hypertension)は、血圧が持続的に正常範囲を超えて高い状態を指します。一般的には、収縮期血圧(SBP)が140 mmHg以上、または拡張期血圧(DBP)が90 mmHg以上の場合を高血圧と定義します。
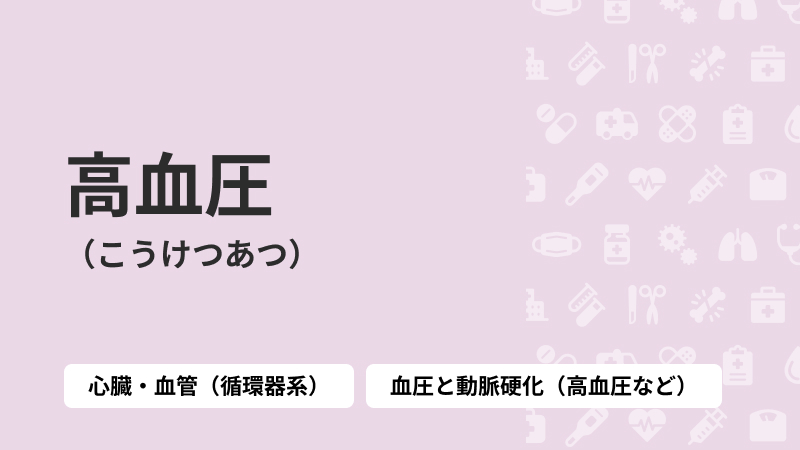
目次
1. 高血圧とは
高血圧(Hypertension)は、血圧が持続的に正常範囲を超えて高い状態を指します。一般的には、収縮期血圧(SBP)が140 mmHg以上、または拡張期血圧(DBP)が90 mmHg以上の場合を高血圧と定義します。
高血圧の基準を図表で示すと以下のようになります。
高血圧の診断基準
| 血圧分類 |
収縮期血圧 (SBP) |
拡張期血圧 (DBP) |
|---|---|---|
|
正常血圧 |
< 120 mmHg |
< 80 mmHg |
|
正常高値血圧 |
120 - 129 mmHg |
< 80 mmHg |
|
1度高血圧 |
130 - 139 mmHg |
80 - 89 mmHg |
|
2度高血圧 |
≥ 140 mmHg |
≥ 90 mmHg |
|
3度高血圧 |
≥ 180 mmHg |
≥ 110 mmHg |
- **正常血圧**: 健康的な状態を示し、特に介入は必要ありません。
- **正常高値血圧**: 血圧が高めですが、まだ高血圧とは診断されません。
- **高血圧 (1度・2度・3度)**: 血圧が基準を超えており、治療や管理が必要です。
しかし、高齢化が進む日本社会においては日本高血圧学会によるガイドラインでは、特に高齢者においては血圧の基準が見直されてきています。特に80歳以上では、血圧の目標値についての見解が分かれることがあります。最近の研究では、150 mmHg未満を目指すことが推奨されることもありますので一度ご相談ください。
2. 日本における高血圧の現状
日本では、高血圧は非常に普及している健康問題です。国民健康・栄養調査によると、高血圧の有病率は30%を超えるとされています。特に、加齢とともにその割合は増加し、60歳以上では約50%に達することもあります。高血圧は心血管疾患や脳卒中などのリスク因子となるため、その管理は重要です。
コラム|欧米と日本はどちらが多い
欧米と日本を比較すると、日本は高血圧の有病率が相対的に高いとされています。具体的には以下の要因が関連しています。
1.食生活の違い
日本:塩分の摂取量が多い伝統的な食事(醤油、味噌などの発酵食品)により、高血圧のリスクが上がる要因となります。
欧米:脂質や糖分の摂取が多いですが、近年は健康志向の高まりもあり、塩分摂取は減少傾向にあります。
2.肥満の有無
欧米では肥満率が高く、肥満は高血圧のリスク因子の一つですが、高血圧への意識や予防策も浸透しています。ビジネス界では肥満や喫煙習慣は自信をコントロールできていないと低い評価を受けることもあるようです。また運動習慣も日本より習慣化されている人が多いようです。
日本では肥満率は比較的低いものの、食塩摂取量の多さや、ストレスなどの生活環境が高血圧に影響を与えています。
3.高血圧に対する医療管理の違い
日本では、特に中高年層で高血圧の管理が課題となっており、生活習慣病としての認知が進んでいます。
欧米では、医療体制や薬の普及により、高血圧の管理が比較的進んでいるとされています。
データによる比較
WHOや各国の調査データによると、日本の高血圧有病率は欧米諸国に比べてやや高めであり、特に高齢者層において顕著です。一方で、欧米でも肥満が関連した高血圧患者が多く、肥満と高血圧の関連が指摘されています。
結論
全体的に見ると、日本の高血圧有病率はやや高めですが、生活習慣や医療管理、意識改善により、どちらの地域でも高血圧予防が進んでいる傾向にあります。
3. 高血圧の原因
高血圧は一次性(本態性)高血圧と二次性高血圧に分けられます。
一次性高血圧: 原因が明確でない場合が多く、遺伝的要因や環境要因(食生活、運動不足、ストレスなど)が関与していると考えられています。
二次性高血圧は、特定の疾患や状態が原因となって血圧が上昇するタイプの高血圧です。以下に、主な原因疾患とその診断に用いられる検査方法を示します。
1. 腎性高血圧
原因疾患:慢性腎臓病、腎動脈狭窄、急性腎炎など
検査方法:
尿検査:タンパク尿や血尿の有無を確認し、腎機能を評価します。
血液検査:クレアチニンや尿素窒素(BUN)などを測定し、腎機能を確認します。
超音波検査:腎臓の形態や大きさを評価し、腎動脈の異常を確認します。
CTやMRI:腎血管の詳細な構造を確認し、腎動脈狭窄の有無を評価します。
2. 内分泌性高血圧
原因疾患:原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫、甲状腺機能亢進症・低下症など
検査方法:
ホルモン検査:
原発性アルドステロン症:血中アルドステロン濃度とレニン活性の測定
クッシング症候群:血中・尿中のコルチゾール濃度、デキサメタゾン抑制試験
褐色細胞腫:血中や尿中のカテコールアミンやその代謝産物(メタネフリン)の測定
甲状腺機能異常:血中TSH、T3、T4の測定
画像検査:
副腎CTやMRI:原発性アルドステロン症や褐色細胞腫を確認
脳下垂体MRI:クッシング症候群の原因となる場合がある下垂体腫瘍の確認
3. 血管性高血圧
原因疾患:大動脈縮窄症(主に若年者)、動脈硬化による血管狭窄など
検査方法:
血圧測定:四肢血圧の比較測定(上下肢での血圧差がある場合、大動脈縮窄症を疑う)
血管造影検査(CTAやMRA):大動脈の狭窄や動脈硬化の程度を確認します。
ドプラー超音波:血流速度や血管の状態を評価します。
4. 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
原因疾患:肥満、上気道の閉塞などが原因となる無呼吸
検査方法:
終夜ポリソムノグラフィー(PSG):睡眠中の呼吸状態、血中酸素濃度、心拍数などを測定し、無呼吸や低呼吸の有無を確認します。
簡易SAS検査:自宅で装着する機器を使用し、睡眠中の呼吸状態や酸素濃度を測定します。
5. その他の原因疾患
甲状腺疾患(甲状腺機能亢進症や低下症)や副甲状腺機能亢進症なども高血圧を引き起こすことがあります。
検査方法:血液検査で甲状腺ホルモンや副甲状腺ホルモンの異常を確認します。
まとめ
二次性高血圧の診断には、原因疾患に応じた詳細な検査が必要です。特に腎臓、内分泌系、血管系の検査が中心となります。高血圧が若年で発症した場合や、一般的な治療に反応しない場合、また症状が急激に悪化した場合には、二次性高血圧が疑われるため、これらの検査を検討します。
4. 高血圧の症状
高血圧自体は「沈黙の殺人者」と呼ばれることがあるように、初期段階では症状がほとんど現れません。しかし、進行することで以下のような症状が現れることがあります。
- 頭痛
- めまい
- 動悸
- 目のかすみ
重度の高血圧では、心不全や脳卒中、腎不全といった重篤な合併症を引き起こす可能性があります。
コラム|高血圧になると何が悪いの?
1. 動脈硬化の進行
高血圧により血管内の圧力が高くなり、血管の内壁(血管内皮細胞)が損傷を受けやすくなります。これが繰り返されると、内壁に傷がつき、そこに脂肪(特にLDLコレステロール)やカルシウムが沈着し、プラーク(動脈壁のこぶのようなもの)を形成します。
プラークが大きくなると動脈が硬くなり、弾力性が失われて血管が狭くなるため、血流が阻害されるリスクが高まります。
2. 心臓への影響(冠動脈硬化と心筋梗塞)
動脈硬化が心臓の冠動脈に発生すると、血液の供給が十分に行き届かなくなり、狭心症(心臓への酸素供給不足)や心筋梗塞(冠動脈が完全に詰まり、心筋が壊死する)が起こりやすくなります。
心筋梗塞は突然起こることが多く、命に関わるリスクが高い病気です。
3. 脳への影響(脳卒中)
動脈硬化が脳に影響すると、脳梗塞や脳出血のリスクが高まります。
脳梗塞:脳の血管がプラークで狭くなり、血流が途絶えて脳細胞が壊死する。
脳出血:動脈硬化で脆くなった血管が破裂し、脳内に出血が起こる。
脳卒中は、運動や言語機能、認知機能などに障害を引き起こし、重い後遺症が残ることもあります。
4. 腎臓への影響
動脈硬化が腎臓の血管に及ぶと、腎臓の血流が悪化し、腎機能が低下します。これにより腎不全や慢性腎臓病(CKD)が進行し、最悪の場合、透析が必要になることもあります。
高血圧と動脈硬化は、腎臓の細い血管を傷つけ、腎機能を損なうため、腎臓病リスクが高まります。
5. 末梢動脈疾患
動脈硬化は足や腕などの末梢動脈にも影響を与え、血流が不足する末梢動脈疾患を引き起こします。このため、歩行中に痛みや痺れを感じることがあります(間欠性跛行)。
6. 動脈瘤(どうみゃくりゅう)
高血圧により脆くなった動脈壁が膨らんで袋状になることがあり、これを動脈瘤といいます。動脈瘤は放置すると破裂のリスクがあり、特に大動脈瘤(腹部や胸部の大動脈)は破裂すると致命的なことが多いです。
まとめ
動脈硬化が進むと、血流が悪くなり、心臓、脳、腎臓などの重要な臓器に影響を与えることで、生命に関わるリスクが高まります。高血圧は動脈硬化の主要な原因の一つであり、血圧を正常に保つことで動脈硬化の進行を防ぎ、これらのリスクを軽減することが可能です。
5.診断方法
高血圧の診断は、血圧測定を通じて行います。診断には、次の方法が用いられます。
家庭での血圧測定: 自宅での測定は、医療機関でのストレスを避けるため有効です。定期的な測定を推奨します。
医療機関での測定: 診察時に血圧を測定し、異常があれば再度測定を行います。
6. 治療と管理
高血圧の治療は、生活習慣の改善と薬物療法の2つのアプローチがあります。
6.1 生活習慣の改善
食事: 塩分の摂取制限や、野菜や果物を多く含むバランスの取れた食事が推奨されます。
コラム|なぜ塩分接種が悪いの?
高血圧の人にとって、塩分制限は血圧管理において重要な役割を果たします。以下のような理由が、塩分制限が必要とされる背景にあります。
### 1. **ナトリウムと血圧の関係**
- 塩分の主成分であるナトリウムは、体内で水分を保持する作用があり、これが血液量を増加させます。血液量が増えると血管にかかる圧力も増すため、血圧が上昇しやすくなります。
- 特に高血圧の人は、ナトリウムに敏感であることが多く、少量の塩分でも血圧が大きく変動する場合があります。
### 2. **血管への負担の軽減**
- 高血圧により血管には常に強い圧力がかかっており、この状態が続くと動脈硬化や血管壁の損傷を引き起こします。塩分を控えることで、血圧が安定し、血管への負担を減らすことができます。
- 血管への負担が軽減されることで、心臓や腎臓、脳などの重要な臓器を守る効果も期待されます。
### 3. **薬の効果を高める**
- 高血圧治療には薬物療法が用いられることが多いですが、塩分を制限することで、薬の効果がより高まりやすくなります。塩分を摂りすぎると薬の効果が弱まることがあり、結果として服薬量が増える可能性があります。
- 塩分制限は薬に頼らない血圧管理を目指す際にも有効です。
### 4. **生活習慣病予防にも役立つ**
- 塩分を制限する食事は、単に血圧を下げるだけでなく、肥満や糖尿病といった他の生活習慣病のリスク低減にもつながります。高血圧とこれらの疾患は相互に影響し合うことが多く、塩分制限による食生活の改善は総合的な健康に寄与します。
### 5. **目標塩分量**
- 一般的に、高血圧の人は1日あたり**6g未満**の塩分摂取が推奨されています。これは日本人の平均摂取量よりも少なく、特に和食は塩分量が多いため注意が必要です。味付けを薄めにする、減塩の調味料を使用するなどの工夫が有効です。
### 塩分制限の具体的な方法
- **調味料の工夫**:減塩醤油や無塩ドレッシングなどを活用する。
- **食材の選び方**:加工食品やインスタント食品は塩分が多いので、できるだけ避ける。
- **出汁やスパイスの活用**:出汁やスパイスを利用して、薄味でも満足できるように工夫する。
### まとめ
塩分制限は、高血圧の管理において大きな効果を発揮します。長期的に血圧を安定させ、薬の量を抑えるためにも、塩分を控える食生活の習慣化が大切です。
運動: 定期的な運動は、血圧を下げるのに効果的です。ウォーキングやジョギング、水泳などが推奨されます。
コラム|なぜ有山荘運動が高血圧にいいのか?
有酸素運動が高血圧に良いとされるのは、以下のような理由があるからです。
1.血管の拡張と柔軟性の向上
有酸素運動を行うと、運動中に酸素が必要とされるため、血管が拡張して血流がスムーズになります。この過程で血管が繰り返し拡張・収縮することで、血管の柔軟性が向上します。
血管が柔軟であると、血流に伴う圧力が分散されやすくなるため、血圧が下がりやすくなります。
2.心臓機能の改善
有酸素運動は、心臓に適度な負荷をかけて鍛えることができます。心臓が効率よく血液を送り出せるようになると、少ない労力で十分な血液を全身に送り出すことができ、心拍数が安定し、血圧も下がりやすくなります。
特に、持続的な有酸素運動は、心臓の収縮力を高め、血圧を下げる効果が持続する傾向があります。
3.体重の減少と代謝改善
有酸素運動によってカロリー消費が促進され、体重の減少につながります。体重が減ると、心臓や血管への負担が軽減され、血圧も低下しやすくなります。
また、運動は基礎代謝を上げるため、肥満やインスリン抵抗性の改善にも効果的で、血圧に悪影響を及ぼす要因を減らすことができます。
4.ストレス軽減による血圧の安定
有酸素運動は、リラックス効果や気分転換にもつながり、ストレスホルモンの分泌を抑制します。ストレスが軽減されると交感神経の過剰な興奮が和らぎ、血管がリラックスして血圧が下がりやすくなります。
運動によるストレスの解消は、日常の精神的な緊張をほぐし、血圧の安定につながります。
5.悪玉コレステロールの低下と動脈硬化予防
有酸素運動は、血中の悪玉コレステロール(LDL)を減らし、善玉コレステロール(HDL)を増加させる効果があります。これにより、動脈硬化のリスクが低減し、血管の健康が保たれるため、血圧の上昇が抑えられます。
6.継続的な効果
定期的な有酸素運動を続けることで、徐々に血圧が安定し、少しの運動でも血圧の低下が得られやすくなります。継続することで、体が運動に慣れ、より少ない努力で健康な状態を維持できるようになります。
有酸素運動の例
ウォーキング:無理なく続けられるため、高血圧の人にも最適。
サイクリングや水泳:関節に負担がかからず、全身の血流を促進できる。
軽いジョギングやエアロビクス:体全体を使い、代謝を高める効果がある。
まとめ
有酸素運動は、血圧を下げるために多角的な効果があり、長期的に血圧管理に寄与します。無理のない範囲で続けることで、心身ともに健康な状態を保ち、血圧のコントロールにも役立ちます。
体重管理: 肥満は高血圧のリスク因子であるため、適正体重を維持することが重要です。
ストレス管理: リラクゼーションや趣味の時間を持つことでストレスを軽減することが助けになります。
6.2薬物療法
生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合、薬物療法が必要です。主な薬剤の種類には以下があります。
利尿薬:体内の余分な水分を排出し、血圧を下げる効果があります。
ACE阻害薬:血管を拡張させ、血圧を下げる作用があります。
カルシウム拮抗薬:血管を弛緩させ、心拍数を抑えることで血圧を下げます。
β遮断薬:心拍数を減少させ、血圧を下げる効果があります。
コラム:最新の薬ARNIとは
7. 高血圧と合併症
高血圧は、心血管系や腎臓に多くの合併症を引き起こす可能性があります。
心血管疾患:動脈硬化や心筋梗塞、心不全のリスクが高まります。
脳卒中:高血圧は脳内の血管を破れる原因となり、脳卒中のリスクを増加させます。
腎不全:腎臓の血管にも影響を与え、慢性腎疾患を引き起こす可能性があります。
8.予防と啓発活動
高血圧の予防には、定期的な健康診断が重要です。また、地域社会や職場での健康教育活動も重要な役割を果たします。日本高血圧学会や各地の医療機関では、高血圧に関する啓発活動を行い、早期発見と治療の重要性を訴えています。
まとめ
高血圧は日本における重大な健康問題であり、適切な管理が求められます。生活習慣の改善や定期的な検査、必要に応じた薬物療法を通じて、健康的な生活を維持することが大切です。高血圧の理解と予防は、個人だけでなく、社会全体の健康にも寄与する重要なテーマです。
症状が気になる場合や、体調に異変を感じたら自分で判断せず、医療機関に相談するようにしましょう。

クラウドドクターの
オンライン診療
クラウドドクターのオンライン診療
クラウドドクターでは、問診内容を元に全国から最適なドクターがマッチングされ、あなたの診療を行います。診療からお薬の処方までビデオ通話で受けられるため、お忙しい方にもおすすめです。
-
24時間365日
いつでも診療OK -
保険診療が
ご利用可能 -
お近くの薬局やご自宅で
お薬の受取り可能
■ この記事を監修した医師

- 公開日:2025/02/07
- 更新日:2025/04/27
クラウドドクターは24時間365日対応
現在の待ち時間
約3分

